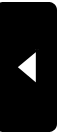【PR】
2018.11.13 新良幸人 with サンデー@Live & Shot.Bar タルマッシュ
2018年11月13日 / 新良幸人/ 仲宗根"サンデー"哲
2018.11.13 新良幸人 with サンデー@Live & Shot.Bar タルマッシュ

出不精になっているうちに琉球フェスティバル以来2か月ライヴから遠ざかり、レポートのブログさえ更新が無いからと広告が出てくる始末でした。ようやく重い腰を上げて向かった今宵は久しぶりの、そして東京ではいつ以来なのか記憶すらない新良幸人さんの唄三線とサンデーさんの太鼓のジョイントライヴです。
場内に登場し、先ずは幸人さんが三線を爪弾き始め、一定のリズムになってくるとそこにサンデーさんの太鼓が重なりジャムっぽい演奏から、挨拶代わりのようにおふたりの育った場所の曲「白保節」のスタートです。お囃子の「ゆらてぃく ゆらてぃく…」もいつもライヴの時にこちらが歌おうかどうしようかドギマギするのですが、今日はサンデーさんにお任せです。曲が終わり「ようやくこの場所に一緒に来る事が出来ました。紹介します。永年の相方、サンデーです。」と紹介する幸人さん。「次の曲は西表の曲で、そんなサンデーに捧げます。」というトークで何の曲だろうと思ったら「デンサー節」…え?語呂合わせ?と爆笑です。幸人さんのソロでのライヴでも良く聴く曲なのですが、太鼓が加わるとひと味もふた味も違った雰囲気になります。いつも不思議にさえ思うのですが、こういうスローな曲だと太鼓というインパクトのある音が加わっているのに、その音が無い時と較べて更に静寂感が増幅され、何というかとても落ち着くのです。
今回関東に来る前、幸人さんは夏川りみさんと南米にツアーで行かれていたそうで、その際の出来事をユーモアたっぷりに語ってくれてか「桃里節」「川良山節」とノリの良い石垣島の民謡が続きます。アップテンポな曲だともちろん太鼓のリズムが一層曲を盛り立ててくれますし、ここでもお囃子や合いの手もサンデーさんにお任せです。「川良山節」の「ゆいさっ」という合いの手のタイミング、ライヴで何度か幸人さんのレクチャーを受けているにも関わらず未だに自信持って入れられないのですが、サンデーさんの合いの手は当たり前ですが憎いほどビタっとハマっていました。
ここでしっとりと歌われたのは幸人さんのライヴでは定番となりつつある「ジントヨーワルツ」で、残念ながら聞き取って直には理解できないのですが歌詞の意味を思い起こしながら聴くと本当に切なくなる曲です。さらに「ファムレウタ」へと続いたのですが、この至高の子守唄にサンデーさんの太鼓が入ると感じるこの完成度は、きっとそのリズムと慈愛に満ちた音は子守唄を歌いながら優しくトントンしてくれる母なり姉なりの手のぬくもりすらも感じる事ができるからなのでしょう。何度体験してもこの感覚はすごいです。
今回はサンデーさんとは初めての場所であったためか、良い意味でグレイテスト・ヒッツ的な展開で、聴きたい曲が目白押しといったセトリです。前半の締めは「ざんざぶろう」こと「高那節」、そして幸人さんの猫撫で声から始まったParsha cluBでもおなじみの「猫小」と八重山の曲が飾ります。せっかくおふたりが揃ったのですから、そりゃ八重山の曲をたっぷり聴きたいですもんね。後半に期待しつつ休憩です。
後半はParsha cluB、そして幸人さんのソロ作品でおなじみの曲が続きます。改めて幸人さんのヴォーカリストとしての素晴らしさが際立つ「赤ゆらの花」で幕を開け、「月ぬ美しゃ」「西武門節」「浜千鳥」ともう有無を言わせぬ鉄板曲が並びます。それも太鼓という彩りを加えての音は何とも贅沢です。こんなにも違うものなのだなぁと再認識しました。
再び南米での出来事を面白おかしく語ってくれて、いつものように「そんな曲です」という強引な結び付けからの「花染手拭」です。この曲、以前はずっと古い民謡だと思っていたのですが、幸人さんの作詞の切ないラヴソングなのですよね。それを知って、なおかつ以前ライヴでこの歌詞を書いた時の背景を聞かせてもらい今まで以上に染み入るようになっているだけに、この毎回異なる内容の強引な結び付けに一体どれがホントなのか見失いそうで大爆笑しちゃいました。
そんな鉄板曲が続いた後は滅多に聴く事がないのではないかなと言う民謡で、僕自身も曲がわからず記憶に残った歌詞を後から検索してこれではないかなという判断なのですが、白保の西側の大浜集落に伝わる「山入らば節」です。どうやら労働歌のようなのですが軽快で楽しい感じの曲でした。続いては僕が大好き曲でライヴで聴きたいと常々思っていながらも、やはり掛け合いの女性ヴォーカルの方がいないとなぁと諦めている「黒島口説」が飛び出したので座席から跳び上がるほどテンションが上がりました。幸人さんがひとりで全てのパートを歌われていたのですが、今回セットインできたのも太鼓というサポートがあったからなのでしょう。僕の席は身体全体の向きが変えられず、ステージを見るには首か腰を捻っていなくてはならなくて、あまりにもキツくて後半は諦めて音を聴くだけにしていたのですが、じっくり聴いていてあれ?っと思ったのですが、この曲は口説部分とお囃子部分のリズムがガラッと変わる、所謂ポリリズムな曲なのかと思っていたのですが、太鼓のリズムを聴いているとリズム自体が変わるのではなくお囃子部分の三線が早弾きになるだけなのではという疑問が生まれたのです。それはそれですごく難しいだろうし、口説に戻った時に三線のピッチも元に戻さないといけないし、それだけに太鼓が不可欠な曲なのかなとも考えました。これは次にどなたかのライヴで「黒島口説」を聴く機会を得た時に、しっかりと目と耳で確かめてみたいポイントです。
佳境に入ってきた感じで続いてのゆいレール車内牧志駅到着メロディ「いちゅび小節」は前回のライヴで「いちごちゃんキターっという曲です」紹介が未だに頭から離れない曲です。そしてラストに待っていたのはソロでもプレイするけどやはりふたりの方がねという「風ゆイヤリ」です。これも幸人さんの胸キュンオリジナルなのですが、最後の部分に笛が入るためソロライヴだとリズムはお客さんの手拍子が頼りになるところ、今宵はサンデーさんがキープしてくれています。安心して笛の音の風にイヤリを乗せて送り出せたことでしょう。ふたりなればこそのこの曲で第二部は終了です。
アンコールに応えてくれて、一足先に戻った幸人さんがひとりで「見上げてごらん夜の星を」のメロディを奏で始めこのまま「満天」?と思いきや、登場したサンデーさんと共に「加那よ」そしてさらにスピードアップして「天川」へ。この展開も太鼓があってこそならではだろうし、早弾きの三線と太鼓のアンサンブルは無条件で聴く者の心を高揚させてくれます。そして待ってましたの「満天の星」で、以前も書きましたが幸人さんの唄三線が描き出すきらめく星空を、サンデーさんの太鼓が打ち出す大海原に小舟を浮かべて見上げているそんな気分にさせてくれる至福の時間です。これで今夜のライヴは終演です。
幸人さんとサンデーさん。
唄三線と太鼓。
音に音が加わり彩りを添え、広がりや奥行きを醸し出し、静寂を敷き、場を盛り上げ、引っ張り、支え、自由に飛び回り、軸を維持する。
たったふたり。
されど最強なふたり。
満たされたこの気持ちは、今夜最後の曲のらラストワンフレーズそのものです。
"我ん心ぬ底や 満天ぬ星よ"


出不精になっているうちに琉球フェスティバル以来2か月ライヴから遠ざかり、レポートのブログさえ更新が無いからと広告が出てくる始末でした。ようやく重い腰を上げて向かった今宵は久しぶりの、そして東京ではいつ以来なのか記憶すらない新良幸人さんの唄三線とサンデーさんの太鼓のジョイントライヴです。
場内に登場し、先ずは幸人さんが三線を爪弾き始め、一定のリズムになってくるとそこにサンデーさんの太鼓が重なりジャムっぽい演奏から、挨拶代わりのようにおふたりの育った場所の曲「白保節」のスタートです。お囃子の「ゆらてぃく ゆらてぃく…」もいつもライヴの時にこちらが歌おうかどうしようかドギマギするのですが、今日はサンデーさんにお任せです。曲が終わり「ようやくこの場所に一緒に来る事が出来ました。紹介します。永年の相方、サンデーです。」と紹介する幸人さん。「次の曲は西表の曲で、そんなサンデーに捧げます。」というトークで何の曲だろうと思ったら「デンサー節」…え?語呂合わせ?と爆笑です。幸人さんのソロでのライヴでも良く聴く曲なのですが、太鼓が加わるとひと味もふた味も違った雰囲気になります。いつも不思議にさえ思うのですが、こういうスローな曲だと太鼓というインパクトのある音が加わっているのに、その音が無い時と較べて更に静寂感が増幅され、何というかとても落ち着くのです。
今回関東に来る前、幸人さんは夏川りみさんと南米にツアーで行かれていたそうで、その際の出来事をユーモアたっぷりに語ってくれてか「桃里節」「川良山節」とノリの良い石垣島の民謡が続きます。アップテンポな曲だともちろん太鼓のリズムが一層曲を盛り立ててくれますし、ここでもお囃子や合いの手もサンデーさんにお任せです。「川良山節」の「ゆいさっ」という合いの手のタイミング、ライヴで何度か幸人さんのレクチャーを受けているにも関わらず未だに自信持って入れられないのですが、サンデーさんの合いの手は当たり前ですが憎いほどビタっとハマっていました。
ここでしっとりと歌われたのは幸人さんのライヴでは定番となりつつある「ジントヨーワルツ」で、残念ながら聞き取って直には理解できないのですが歌詞の意味を思い起こしながら聴くと本当に切なくなる曲です。さらに「ファムレウタ」へと続いたのですが、この至高の子守唄にサンデーさんの太鼓が入ると感じるこの完成度は、きっとそのリズムと慈愛に満ちた音は子守唄を歌いながら優しくトントンしてくれる母なり姉なりの手のぬくもりすらも感じる事ができるからなのでしょう。何度体験してもこの感覚はすごいです。
今回はサンデーさんとは初めての場所であったためか、良い意味でグレイテスト・ヒッツ的な展開で、聴きたい曲が目白押しといったセトリです。前半の締めは「ざんざぶろう」こと「高那節」、そして幸人さんの猫撫で声から始まったParsha cluBでもおなじみの「猫小」と八重山の曲が飾ります。せっかくおふたりが揃ったのですから、そりゃ八重山の曲をたっぷり聴きたいですもんね。後半に期待しつつ休憩です。
後半はParsha cluB、そして幸人さんのソロ作品でおなじみの曲が続きます。改めて幸人さんのヴォーカリストとしての素晴らしさが際立つ「赤ゆらの花」で幕を開け、「月ぬ美しゃ」「西武門節」「浜千鳥」ともう有無を言わせぬ鉄板曲が並びます。それも太鼓という彩りを加えての音は何とも贅沢です。こんなにも違うものなのだなぁと再認識しました。
再び南米での出来事を面白おかしく語ってくれて、いつものように「そんな曲です」という強引な結び付けからの「花染手拭」です。この曲、以前はずっと古い民謡だと思っていたのですが、幸人さんの作詞の切ないラヴソングなのですよね。それを知って、なおかつ以前ライヴでこの歌詞を書いた時の背景を聞かせてもらい今まで以上に染み入るようになっているだけに、この毎回異なる内容の強引な結び付けに一体どれがホントなのか見失いそうで大爆笑しちゃいました。
そんな鉄板曲が続いた後は滅多に聴く事がないのではないかなと言う民謡で、僕自身も曲がわからず記憶に残った歌詞を後から検索してこれではないかなという判断なのですが、白保の西側の大浜集落に伝わる「山入らば節」です。どうやら労働歌のようなのですが軽快で楽しい感じの曲でした。続いては僕が大好き曲でライヴで聴きたいと常々思っていながらも、やはり掛け合いの女性ヴォーカルの方がいないとなぁと諦めている「黒島口説」が飛び出したので座席から跳び上がるほどテンションが上がりました。幸人さんがひとりで全てのパートを歌われていたのですが、今回セットインできたのも太鼓というサポートがあったからなのでしょう。僕の席は身体全体の向きが変えられず、ステージを見るには首か腰を捻っていなくてはならなくて、あまりにもキツくて後半は諦めて音を聴くだけにしていたのですが、じっくり聴いていてあれ?っと思ったのですが、この曲は口説部分とお囃子部分のリズムがガラッと変わる、所謂ポリリズムな曲なのかと思っていたのですが、太鼓のリズムを聴いているとリズム自体が変わるのではなくお囃子部分の三線が早弾きになるだけなのではという疑問が生まれたのです。それはそれですごく難しいだろうし、口説に戻った時に三線のピッチも元に戻さないといけないし、それだけに太鼓が不可欠な曲なのかなとも考えました。これは次にどなたかのライヴで「黒島口説」を聴く機会を得た時に、しっかりと目と耳で確かめてみたいポイントです。
佳境に入ってきた感じで続いてのゆいレール車内牧志駅到着メロディ「いちゅび小節」は前回のライヴで「いちごちゃんキターっという曲です」紹介が未だに頭から離れない曲です。そしてラストに待っていたのはソロでもプレイするけどやはりふたりの方がねという「風ゆイヤリ」です。これも幸人さんの胸キュンオリジナルなのですが、最後の部分に笛が入るためソロライヴだとリズムはお客さんの手拍子が頼りになるところ、今宵はサンデーさんがキープしてくれています。安心して笛の音の風にイヤリを乗せて送り出せたことでしょう。ふたりなればこそのこの曲で第二部は終了です。
アンコールに応えてくれて、一足先に戻った幸人さんがひとりで「見上げてごらん夜の星を」のメロディを奏で始めこのまま「満天」?と思いきや、登場したサンデーさんと共に「加那よ」そしてさらにスピードアップして「天川」へ。この展開も太鼓があってこそならではだろうし、早弾きの三線と太鼓のアンサンブルは無条件で聴く者の心を高揚させてくれます。そして待ってましたの「満天の星」で、以前も書きましたが幸人さんの唄三線が描き出すきらめく星空を、サンデーさんの太鼓が打ち出す大海原に小舟を浮かべて見上げているそんな気分にさせてくれる至福の時間です。これで今夜のライヴは終演です。
幸人さんとサンデーさん。
唄三線と太鼓。
音に音が加わり彩りを添え、広がりや奥行きを醸し出し、静寂を敷き、場を盛り上げ、引っ張り、支え、自由に飛び回り、軸を維持する。
たったふたり。
されど最強なふたり。
満たされたこの気持ちは、今夜最後の曲のらラストワンフレーズそのものです。
"我ん心ぬ底や 満天ぬ星よ"

Posted by Ken2 at
23:59
│Comments(0)
2018.9.23 琉球フェスティバル2018@日比谷野外大音楽堂
2018年09月23日 / 新良幸人/ よなは徹/ Parsha cluB/ その他(沖縄)
2018.9.23 琉球フェスティバル2018@日比谷野外大音楽堂

今年も年に一度のお楽しみ、琉球フェスティバルの日を迎えました。記録的な猛暑の長かった夏が終わり、ようやく過ごしやすい季節になったものの、去りゆく夏を惜しむかのように少し気温が上昇した日曜の午後、日比谷野音には2500人を超える沖縄音楽好きが集結しました。恒例のエイサー演舞にひきつづき、司会進行のガレッジセールと久保田アナウンサーがステージに登場し、いつもの通り開幕です。ガレッジセールのゴリさんがいつも琉フェスのステージでは、お客さんがお酒を差し入れてくれて飲み干すのが恒例ですが、昨今これはパワハラに当たるとされスタッフに止められたとの話。「いいですかみなさん!これが『コンプライアンス』というものです!」と笑いを交えて伝えていました。確かに毎回お客さんが面白がってガレッジセールに飲ませていたのはいかがなものかとは思っていましたが、それとは別にこの祭りというハレの日に「コンプライアンス」などと横文字を使っての規制にもなんだか世知辛い世の中になったなぁという気持ちになったのも事実です。

4時間近くに及ぶライヴのトップバッターは宮沢和史さんで、三線の大城クラウディアを含むフルバンドでのセットでした。7年前の世界のウチナーンチュ大会サポートソングだった「シンカヌチャー」でスタートしたのですが、「仲間」を意味するこの曲はどこで生まれて育ったとしても、沖縄を愛し、その文化を尊重し、歌い踊れば仲間であり、そこは沖縄になると歌っており、琉フェスの幕開けにはふさわしい曲でした。民謡を含めて最後の「島唄」までのセットは沖縄音楽色の濃い、きっちりまとまったものであったのですが、僕は妙な違和感を感じてしまいました。どんなにその文化を愛し造詣が深くなったとしても、シンカヌチャーの想いとは相反するものにはなってしまいますが沖縄色の「色」はあくまで「色」なのかもしれないなぁという複雑な心境でした。もしかしたら同じ沖縄県外の人間だからこそ、かえって「これは違う」と排他的になってしまうのかもしれません。それでも「島唄」での場内大合唱は、天候に恵まれた野外ライヴならではの音の広がりが素敵な時間をもたらしてくれました。

次は奄美からの里アンナさん。僕は彼女のステージは初めてなのですが度胆を抜かれました。ドラマーとふたりというめずらしい構成です。同じ文化圏にありながらも歌い方から発声法まで沖縄のそれとはちがっており、特に1曲目はメロディーラインも歌い方もまるで中央アジアの伝統音楽のようなエキゾティックさで、ベタな表現ですが天上の音楽のようでした。奄美竪琴と呼ばれる小型の琴を縦に構えて演奏する姿も天女のようでした。大河ドラマ「西郷どん」の曲をアカペラで披露してくれてからの後半は三線に持ち替えて奄美の民謡へ。奄美のご出身の方なのかたまらずに踊り出すお客さんも続出して良い雰囲気になってきました。最後のノリの良い「ワイド節」では気持ち良く踊っていらっしゃるお客さんが、途中に組み入れられたドラムソロで流れが途切れた感じでした。ライヴの表現方法としては充分にわかるのですが、民謡を洋楽器とのコラボで演奏する難しさであるのかもしれません。特に琉フェスという祭りのステージでは尚更そう感じました。それはそれとしても素晴らしいアーティストとの出会いでした。

三番手は琉球オールスターズと名乗るスーパーユニットで、先ずは徳原清文さんと元ちゃんこと前川守賢さんの唄・三線とよなは徹さんの太鼓という組み合わせで真境名由佳子さんも舞踊で参加です。お二方がそれぞれにヴォーカルを取られた曲も含め安定感のあるステージです。

そのお二方と入れ替わって登場は昨年芸能生活60周年を迎えられた大御所・大城美佐子さんの登場です。太鼓でサポートの徹さんが「弾き始めるまで何を唄うのかわかりませんし、太鼓が必要なのかもわかりません。」と紹介から始まったのは太鼓も入る「白雲節」です。美佐子さんはこの一曲のみでしたが、その存在感を示してくれました。

続いてはよなは徹さんのバンドセットです。セットチェンジの間に色紋付・袴姿からユニオンジャック柄が鮮やかなシャツ姿に着替えて徹さんが登場すると、意表を突いて「チョンチョンキジムナー」でスタートです。いつもひとり歌会で見慣れている徹さんですが、バンド編成でのステージは水を得た魚の如く活き活きとステージで、じっくりと古典を聴かせてくれる時とはまた違った面を見せてくれます。

盛り上がる事必至の「花の風車」「唐船どーい」も、厚みのあるバンドサウンドでかっこいい!の一言で、お客さんもたまらずに立ち上がってのカチャーシーです。その興奮を落ち着かせるかのように古典曲からのキラーチューン「満月の夕」へ。暮れなずみつつある空に心地よく響きます。東京で沖縄のアーティスのライヴが開催される機会はたくさんあるのですが、店舗系の会場でありこじんまりしている事が多いので、大音響でなおかつ開放感のある野音で聴くことのできる琉フェスは年に一度だけ味わえる醍醐味です。毎年思う事ですが、ライヴハウスでいいからバンド編成で徹さんのフルライヴを体験したいなと思いました。

夜の帳が降りはじめてきた頃、八重山民謡のレジェンド・大工哲弘さんの登場です。琴と舞踊をこなす奥様の苗子さんと、お弟子さんの伊藤幸太さん、太鼓のサポートでのセットです。相変わらず親父ギャグ満載のトークで盛り上げつつ進行していきます。途中今日は大忙しの徹さんが笛で参加しての名曲「とぅばらーま」は聴き惚れる程でした。最後は藤島桓夫さんの「さよなら港」だったのですが、八重山でいまでも愛され続けているこの昭和歌謡の存在が僕には不思議でなりません。もう60年以上前の歌謡曲なのですが、お祭りなどでは定番曲のようで異様に盛り上がるのです。昔は就職なので島を離れるときには船だったはずですから、生活に密着した曲だったのかもしれません。苗子さんが面白おかしい踊りでステージ狭しと動き回り、紙テープを投げて更に盛り上げてくれました。

そしていよいよ待ちに待った大トリ、Parsha cluBの登場です。例年通り通路を埋めるくらい前に出てきてスタンバイするお客さんも含めて総立ちでその登場を迎えました。毎年旬の仮装で楽しませてくれる幸人さんが今年はどんな出で立ちなのかにも注目が集まります。安室ちゃんじゃないか?ひょっこりはんでは?大坂なおみさん?と色々な予想が聞こえていましたが、出てきた幸人さんは白いトレーニングウェア上下に胸には沖縄県マーク、背中には「ジャパン」と書かれたマジック文字、帽子にサングラスという姿。まさかの日本ボクシング連盟の山根会長コスプレです。そこ突いてくる!?という発想で大爆笑です。そして昨年の琉フェス以来Parshaにとっても一年ぶりのステージはもちろん「海の彼方」でのスタートです。総立ちのお客さんも一緒に手を挙げて応え、一気にワクワク感はピークに達しました。

山根会長ネタのトークで湧かせてから幸人さんは早くもコスプレを脱ぎ去り、サンデーさんのパーカッションがリズムを取り始め2曲目の「東バンタ」へ。途中ふと気づいたのですが、フルコーラスを一緒に歌っている自分ですが歌詞の意味を把握していないなぁと。あくまで耳で憶えているのであり、例えばフランス語とか話せない他言語の歌を一緒に歌っているような感覚だと思うとおかしくなってきました。

間髪入れずにスタートした3曲目の「五穀豊穣」。やはりこのバンド、唯一無二のかっこよさです。こちらの息まで上がった3曲のあと、幸人さんの奏でる三線の一音一音がすっかり暗くなった空に昇ってゆき輝きはじめ「満天の星」です。ステージ上の6人の紡ぎだす音のタペストリーに包まれうっとりする至福の時間です。まだまだ聴きたい!もっとやって欲しい!あの曲を聴きたい!という想いが溢れる琉フェスのセットですが、それはワンマン・ライヴのお楽しみに取っておくとして、今年もこうしてParshaのステージを体験できただけで幸せな気分になりました。

興奮冷めやらない中登場し、「コンプライアンス」という名の圧力と、お客さんを楽しませたい、楽しんでもらいたいという強い思いの板挟みになりつつもがんばって進行してくれ、かわいそうにさえ思えた司会のお三方にも本当にお疲れ様と言いたいです。最後のセットチェンジの間の繋ぎのトークにもそんな気持ちが溢れていました。

そしてフィナーレ。出演者全員が登場しての「豊年音頭」と「唐船どーい」で、例年通り日比谷野音は民族の祭典のような興奮の坩堝と化して幕を閉じました。前述の繋ぎトークでガレッジセールのゴリさんが話していたように、集まった僕たちは終わってしまった年に一度の祭りの会場を後にして、仕事や家庭の日常生活へと戻っていくしかありません。その何かに追われ続ける日々の向こう側に来年のこの祭りがあることを信じ、それが頑張る糧となっていく事でしょう。ライヴとして考えれば、それぞれのアーティストをもっとじっくり聴きたいとか、せっかくの機会だから意外な組み合わせのコラボレーションがあったら嬉しいなと思う点はあります。マンネリ化してきていて変わり映えがしないと言った感想も耳にします。それでも僕にとって琉フェスは「祭り」なのです。年に一度この日だけ一堂に会するアーティストたちに加えて、この日くらいしか会えない友人たちの笑顔に接すると、今年もこの日を迎えることができたのだなという喜びでいっぱいになるのです。それが「祭り」なのです。

今年も年に一度のお楽しみ、琉球フェスティバルの日を迎えました。記録的な猛暑の長かった夏が終わり、ようやく過ごしやすい季節になったものの、去りゆく夏を惜しむかのように少し気温が上昇した日曜の午後、日比谷野音には2500人を超える沖縄音楽好きが集結しました。恒例のエイサー演舞にひきつづき、司会進行のガレッジセールと久保田アナウンサーがステージに登場し、いつもの通り開幕です。ガレッジセールのゴリさんがいつも琉フェスのステージでは、お客さんがお酒を差し入れてくれて飲み干すのが恒例ですが、昨今これはパワハラに当たるとされスタッフに止められたとの話。「いいですかみなさん!これが『コンプライアンス』というものです!」と笑いを交えて伝えていました。確かに毎回お客さんが面白がってガレッジセールに飲ませていたのはいかがなものかとは思っていましたが、それとは別にこの祭りというハレの日に「コンプライアンス」などと横文字を使っての規制にもなんだか世知辛い世の中になったなぁという気持ちになったのも事実です。

4時間近くに及ぶライヴのトップバッターは宮沢和史さんで、三線の大城クラウディアを含むフルバンドでのセットでした。7年前の世界のウチナーンチュ大会サポートソングだった「シンカヌチャー」でスタートしたのですが、「仲間」を意味するこの曲はどこで生まれて育ったとしても、沖縄を愛し、その文化を尊重し、歌い踊れば仲間であり、そこは沖縄になると歌っており、琉フェスの幕開けにはふさわしい曲でした。民謡を含めて最後の「島唄」までのセットは沖縄音楽色の濃い、きっちりまとまったものであったのですが、僕は妙な違和感を感じてしまいました。どんなにその文化を愛し造詣が深くなったとしても、シンカヌチャーの想いとは相反するものにはなってしまいますが沖縄色の「色」はあくまで「色」なのかもしれないなぁという複雑な心境でした。もしかしたら同じ沖縄県外の人間だからこそ、かえって「これは違う」と排他的になってしまうのかもしれません。それでも「島唄」での場内大合唱は、天候に恵まれた野外ライヴならではの音の広がりが素敵な時間をもたらしてくれました。

次は奄美からの里アンナさん。僕は彼女のステージは初めてなのですが度胆を抜かれました。ドラマーとふたりというめずらしい構成です。同じ文化圏にありながらも歌い方から発声法まで沖縄のそれとはちがっており、特に1曲目はメロディーラインも歌い方もまるで中央アジアの伝統音楽のようなエキゾティックさで、ベタな表現ですが天上の音楽のようでした。奄美竪琴と呼ばれる小型の琴を縦に構えて演奏する姿も天女のようでした。大河ドラマ「西郷どん」の曲をアカペラで披露してくれてからの後半は三線に持ち替えて奄美の民謡へ。奄美のご出身の方なのかたまらずに踊り出すお客さんも続出して良い雰囲気になってきました。最後のノリの良い「ワイド節」では気持ち良く踊っていらっしゃるお客さんが、途中に組み入れられたドラムソロで流れが途切れた感じでした。ライヴの表現方法としては充分にわかるのですが、民謡を洋楽器とのコラボで演奏する難しさであるのかもしれません。特に琉フェスという祭りのステージでは尚更そう感じました。それはそれとしても素晴らしいアーティストとの出会いでした。

三番手は琉球オールスターズと名乗るスーパーユニットで、先ずは徳原清文さんと元ちゃんこと前川守賢さんの唄・三線とよなは徹さんの太鼓という組み合わせで真境名由佳子さんも舞踊で参加です。お二方がそれぞれにヴォーカルを取られた曲も含め安定感のあるステージです。

そのお二方と入れ替わって登場は昨年芸能生活60周年を迎えられた大御所・大城美佐子さんの登場です。太鼓でサポートの徹さんが「弾き始めるまで何を唄うのかわかりませんし、太鼓が必要なのかもわかりません。」と紹介から始まったのは太鼓も入る「白雲節」です。美佐子さんはこの一曲のみでしたが、その存在感を示してくれました。

続いてはよなは徹さんのバンドセットです。セットチェンジの間に色紋付・袴姿からユニオンジャック柄が鮮やかなシャツ姿に着替えて徹さんが登場すると、意表を突いて「チョンチョンキジムナー」でスタートです。いつもひとり歌会で見慣れている徹さんですが、バンド編成でのステージは水を得た魚の如く活き活きとステージで、じっくりと古典を聴かせてくれる時とはまた違った面を見せてくれます。

盛り上がる事必至の「花の風車」「唐船どーい」も、厚みのあるバンドサウンドでかっこいい!の一言で、お客さんもたまらずに立ち上がってのカチャーシーです。その興奮を落ち着かせるかのように古典曲からのキラーチューン「満月の夕」へ。暮れなずみつつある空に心地よく響きます。東京で沖縄のアーティスのライヴが開催される機会はたくさんあるのですが、店舗系の会場でありこじんまりしている事が多いので、大音響でなおかつ開放感のある野音で聴くことのできる琉フェスは年に一度だけ味わえる醍醐味です。毎年思う事ですが、ライヴハウスでいいからバンド編成で徹さんのフルライヴを体験したいなと思いました。
夜の帳が降りはじめてきた頃、八重山民謡のレジェンド・大工哲弘さんの登場です。琴と舞踊をこなす奥様の苗子さんと、お弟子さんの伊藤幸太さん、太鼓のサポートでのセットです。相変わらず親父ギャグ満載のトークで盛り上げつつ進行していきます。途中今日は大忙しの徹さんが笛で参加しての名曲「とぅばらーま」は聴き惚れる程でした。最後は藤島桓夫さんの「さよなら港」だったのですが、八重山でいまでも愛され続けているこの昭和歌謡の存在が僕には不思議でなりません。もう60年以上前の歌謡曲なのですが、お祭りなどでは定番曲のようで異様に盛り上がるのです。昔は就職なので島を離れるときには船だったはずですから、生活に密着した曲だったのかもしれません。苗子さんが面白おかしい踊りでステージ狭しと動き回り、紙テープを投げて更に盛り上げてくれました。

そしていよいよ待ちに待った大トリ、Parsha cluBの登場です。例年通り通路を埋めるくらい前に出てきてスタンバイするお客さんも含めて総立ちでその登場を迎えました。毎年旬の仮装で楽しませてくれる幸人さんが今年はどんな出で立ちなのかにも注目が集まります。安室ちゃんじゃないか?ひょっこりはんでは?大坂なおみさん?と色々な予想が聞こえていましたが、出てきた幸人さんは白いトレーニングウェア上下に胸には沖縄県マーク、背中には「ジャパン」と書かれたマジック文字、帽子にサングラスという姿。まさかの日本ボクシング連盟の山根会長コスプレです。そこ突いてくる!?という発想で大爆笑です。そして昨年の琉フェス以来Parshaにとっても一年ぶりのステージはもちろん「海の彼方」でのスタートです。総立ちのお客さんも一緒に手を挙げて応え、一気にワクワク感はピークに達しました。

山根会長ネタのトークで湧かせてから幸人さんは早くもコスプレを脱ぎ去り、サンデーさんのパーカッションがリズムを取り始め2曲目の「東バンタ」へ。途中ふと気づいたのですが、フルコーラスを一緒に歌っている自分ですが歌詞の意味を把握していないなぁと。あくまで耳で憶えているのであり、例えばフランス語とか話せない他言語の歌を一緒に歌っているような感覚だと思うとおかしくなってきました。
間髪入れずにスタートした3曲目の「五穀豊穣」。やはりこのバンド、唯一無二のかっこよさです。こちらの息まで上がった3曲のあと、幸人さんの奏でる三線の一音一音がすっかり暗くなった空に昇ってゆき輝きはじめ「満天の星」です。ステージ上の6人の紡ぎだす音のタペストリーに包まれうっとりする至福の時間です。まだまだ聴きたい!もっとやって欲しい!あの曲を聴きたい!という想いが溢れる琉フェスのセットですが、それはワンマン・ライヴのお楽しみに取っておくとして、今年もこうしてParshaのステージを体験できただけで幸せな気分になりました。

興奮冷めやらない中登場し、「コンプライアンス」という名の圧力と、お客さんを楽しませたい、楽しんでもらいたいという強い思いの板挟みになりつつもがんばって進行してくれ、かわいそうにさえ思えた司会のお三方にも本当にお疲れ様と言いたいです。最後のセットチェンジの間の繋ぎのトークにもそんな気持ちが溢れていました。

そしてフィナーレ。出演者全員が登場しての「豊年音頭」と「唐船どーい」で、例年通り日比谷野音は民族の祭典のような興奮の坩堝と化して幕を閉じました。前述の繋ぎトークでガレッジセールのゴリさんが話していたように、集まった僕たちは終わってしまった年に一度の祭りの会場を後にして、仕事や家庭の日常生活へと戻っていくしかありません。その何かに追われ続ける日々の向こう側に来年のこの祭りがあることを信じ、それが頑張る糧となっていく事でしょう。ライヴとして考えれば、それぞれのアーティストをもっとじっくり聴きたいとか、せっかくの機会だから意外な組み合わせのコラボレーションがあったら嬉しいなと思う点はあります。マンネリ化してきていて変わり映えがしないと言った感想も耳にします。それでも僕にとって琉フェスは「祭り」なのです。年に一度この日だけ一堂に会するアーティストたちに加えて、この日くらいしか会えない友人たちの笑顔に接すると、今年もこの日を迎えることができたのだなという喜びでいっぱいになるのです。それが「祭り」なのです。
Posted by Ken2 at
23:59
│Comments(0)
2018.6.22 ◎ターシ@Bar YAYA Ebisu
2018年06月22日 / ◎ターシ
2018.6.22 ◎ターシ このうえないLIVE!東京@Bar YAYA Ebisu

2ヵ月に一度、東京・恵比寿のバーで開催される◎ターシさんのライヴ。昨年末から行くようになって今回で4回目となり、会場に集う◎ターシ・マニアの方々ともだんだん顔見知りとなり挨拶を交わすまでになってきました。失礼ながら決して多い人数ではないのですが、僕にとってはそのじっくりと音楽に接することができる時間こそがこのバー・ライヴの魅力であり、たとえば家から歩いて数分のところに居酒屋さんがあり、そこで定期的にライヴがあっても宴会のBGM扱いのような喧噪の中で聴かなくてはならないのであれば足繁く通うことはないと思います。

2ヵ月前は日曜の開催で「サンデー・ナイト・バラード・ライヴ」となり、しっとりとした曲が多かったのですが、今夜は「パスポートもって」でスタートです。明るく爽やかな曲なのですが、アメリカ統治下の沖縄の少年がパスポートを手に2泊3日の船旅で東京、大阪にやってくるという歌詞で、◎ターシさんの世代だからこそ書ける曲であり、僕の中ではとても深く貴重な存在感のある曲です。

続いて梅雨の合間の今日にぴったりな、ひと足早く夏を感じさせてくれる「daydream」でウキウキさせてくれ、もう1曲挟んで数あるカヴァー・レパートリーからリチャード・マークスの「Now and Forever」へと続きます。ここのところちょっとネガティブ・モードに入っていて、こんな時はそんな歌詞の曲を作ろうと思い立ち、頭に出て来るネガティブなコトバを書きとめようとしたら浮かんでこなくて、結局ボキャブラリーが少ないなぁという思いでネガネガな気分になったという話がネガティブなのに妙におかしかったです。◎ターシさんのこういう話を聞いているととても哲学的で、常に物事を深く考えているのだなぁと思い、自分の浅はかさが恥ずかしくなります。妄想好きな点は同じなのになぁ。

ライヴで聴くうちにすでにお馴染みになったオリジナル曲「アルバム」に続いて、静かなギターのイントロで歌い始めたのは”ざわわ ざわわ ざわわ…”、そう「さとうきび畑」です。意外な曲が飛び出してびっくりしましたが、そうか明日は6月23日沖縄慰霊の日です。曲の途中ギターを爪弾きながらミュージシャン仲間の伊集タツヤさんがSNSに投稿していたのですが、慰霊の日はアメリカ兵、日本兵、沖縄住民、亡くなった全ての方を思い祈る日であるという話をされ、それが僕にとってはとても大きな意味を持つ話でした。慰霊の日というと沖縄戦で尊い生命を落とされた住民の方々の慰霊という意識があったのですが、それだけではなく味方も敵もなく犠牲になったすべての御霊を慰めるものなのですよね。僕の伯父は戦闘が終わる5日前に沖縄戦で戦死しており、その部隊の慰霊碑が糸満にあります。その場所を訪れるためにそもそも僕が沖縄と繋がったのであり、7年前に三十数年ぶりに訪れた際に慰霊碑から平和祈念公園へと行き、タクシーの運転手さんが僕がその存在すら知らなかった”平和の礎”の事を教えてくれ、伯父の名前もあるはずよーと一緒に探してくれたのです。見つけた時、その場にいる自分が途切れていた縦の線で繋がったかのような、なにかこう雷に打たれたような感覚となったのは今でも忘れられません。そしてこうして、伯父の名が一緒に刻まれていることがとてつもなくありがたかったのです。沖縄慰霊の日とはそういう広い心が根底にあるのだなと、今夜感謝の念を新たにしました。そこから流れるように続いた「花鳥風水」もまるでレクイエムのように響き、ここで短い休憩に入りました。

後半は「僕と空の間」「あかばなー」「細い三日月と満天の星」などのオリジナル曲が続きます。僕にとってはライヴでしか聴くことができない曲も多いのですが、聴くたびに違って響きます。◎ターシさんが語っていたのですがライヴで演奏する度に曲が磨かれて成長していくという事が実際にわかるような気がします。決して前回がダメだったというのではなく、回を重ねるごとに曲が魅力的になっていくのですから成長という言葉がぴったりに感じます。

そして2曲カヴァーが続いたのですが、まずは「Time After Time」。この曲はとても高いキーで歌われ、時々苦しそうに感じる事もあるのですが、今夜の声のコンディションはいつにも増して素晴らしく、続く「Can’t Help Falling in Love」は低音部から高音までもう鳥肌立つほどの美しさで、オジサンがオジサンにうっとりしちゃいました。

ここからはオリジナル曲で進みます。雪の札幌を歌った「SPK」、季節感を出そうねと「夏のモザイク」、僕にとっては初めて◎ターシさんのことを知った出会いの曲で一耳惚れした「じゅーしぃ食べたらいいさぁ」という流れに、安定の心地よさを感じます。前述のように同じ曲がセットインしても毎回違った響きをするので飽きることはありません。ソロでの弾き語りという事もあるのでしょうが、1曲1曲毎回その日だけのヴァージョンになっているかのようです。

そして「通学路」「いつも君がそばにいて」と昭和感漂う甘酸っぱい曲が並びましたが、とても好きな雰囲気です。ご本人はこういう曲は難しい、意外かもしれないけれど歌うのが恥ずかしくなると語っていましたが、聴いている昭和感満載の我々としては、その甘酸っぱい歌詞によって自分の青春時代に時間旅行へと連れて行ってもらっているような感覚になるのです。

この会場は22時には終演となっているので、あぁこれで最後だな、アンコールは無しだなとわかりやすくお客さんもそれを承知しており、それでも無理矢理1曲でも多く聴いた方がお得だというガツガツした感じがなくて好きなのですが、ちょうどあと1曲の時間となり◎ターシさんの選んだ曲は「ふくぎ」でした。これも多分毎回歌われている曲なのですが、今夜はいつもと大きく違って響きました。というのも今までこの曲の紹介のときには自宅の近くにフクギ並木があって、その実が落ちると臭いとか、それを餌にするリュウキュウオオコオモリがでかいなどという内容だったので、明るい曲だなぁくらいのイメージだったのですが、今夜の話は木を一本ずつ植えていく男の話に触れ、最初は周囲の人にバカにされていたものの何年もして大きな森になった時には人々の尊敬と感謝を集めたという昔話が大好きで、そこからの妄想でフクギの並木は各地にあるけれどあまり森はない。例えば嘉手納基地に、もし1本ずつフクギを植えていって、何年も何年もして広大な森となり、そこを歩くと遺跡のようにみんながその存在を忘れた軍の施設があったら楽しいなという思いで書いたという話を初めて聞いてからの演奏だったので、”アカズノトビラ”のような今まではどんな意味があるのだろうと思っていた、というよりも考えることさえないまま耳に入ってきていた歌詞にもその意味や整合性を見い出し、なるほどこういう内容の曲だったのかと合点がいったのです。もちろん歌詞に関してはそれぞれ聴く側がどう感じ何を思うかなのでしょうし、背景を説明されて逆に受け止め方が限定されてしまう場合もあるのですが、この曲に関してはわかった事でさらにしっかりと受け止められるようになったと思います。

こうして恒例のこのうえないLIVE!東京は終演しました。僕にとっては、◎ターシさん自身は特に想いを込めたとか、意識したということもないはずなのですが「慰霊の日」を意識し考えさせてもらえた特別なライヴになりました。そして毎回の事ながら、慌ただしい日常の生活の中で、2ヵ月に一度その音楽と歌声で肩のチカラをふっと抜いてくれるオトナの時間を持てた事に幸せを感じた夜でした。
2ヵ月に一度、東京・恵比寿のバーで開催される◎ターシさんのライヴ。昨年末から行くようになって今回で4回目となり、会場に集う◎ターシ・マニアの方々ともだんだん顔見知りとなり挨拶を交わすまでになってきました。失礼ながら決して多い人数ではないのですが、僕にとってはそのじっくりと音楽に接することができる時間こそがこのバー・ライヴの魅力であり、たとえば家から歩いて数分のところに居酒屋さんがあり、そこで定期的にライヴがあっても宴会のBGM扱いのような喧噪の中で聴かなくてはならないのであれば足繁く通うことはないと思います。
2ヵ月前は日曜の開催で「サンデー・ナイト・バラード・ライヴ」となり、しっとりとした曲が多かったのですが、今夜は「パスポートもって」でスタートです。明るく爽やかな曲なのですが、アメリカ統治下の沖縄の少年がパスポートを手に2泊3日の船旅で東京、大阪にやってくるという歌詞で、◎ターシさんの世代だからこそ書ける曲であり、僕の中ではとても深く貴重な存在感のある曲です。
続いて梅雨の合間の今日にぴったりな、ひと足早く夏を感じさせてくれる「daydream」でウキウキさせてくれ、もう1曲挟んで数あるカヴァー・レパートリーからリチャード・マークスの「Now and Forever」へと続きます。ここのところちょっとネガティブ・モードに入っていて、こんな時はそんな歌詞の曲を作ろうと思い立ち、頭に出て来るネガティブなコトバを書きとめようとしたら浮かんでこなくて、結局ボキャブラリーが少ないなぁという思いでネガネガな気分になったという話がネガティブなのに妙におかしかったです。◎ターシさんのこういう話を聞いているととても哲学的で、常に物事を深く考えているのだなぁと思い、自分の浅はかさが恥ずかしくなります。妄想好きな点は同じなのになぁ。
ライヴで聴くうちにすでにお馴染みになったオリジナル曲「アルバム」に続いて、静かなギターのイントロで歌い始めたのは”ざわわ ざわわ ざわわ…”、そう「さとうきび畑」です。意外な曲が飛び出してびっくりしましたが、そうか明日は6月23日沖縄慰霊の日です。曲の途中ギターを爪弾きながらミュージシャン仲間の伊集タツヤさんがSNSに投稿していたのですが、慰霊の日はアメリカ兵、日本兵、沖縄住民、亡くなった全ての方を思い祈る日であるという話をされ、それが僕にとってはとても大きな意味を持つ話でした。慰霊の日というと沖縄戦で尊い生命を落とされた住民の方々の慰霊という意識があったのですが、それだけではなく味方も敵もなく犠牲になったすべての御霊を慰めるものなのですよね。僕の伯父は戦闘が終わる5日前に沖縄戦で戦死しており、その部隊の慰霊碑が糸満にあります。その場所を訪れるためにそもそも僕が沖縄と繋がったのであり、7年前に三十数年ぶりに訪れた際に慰霊碑から平和祈念公園へと行き、タクシーの運転手さんが僕がその存在すら知らなかった”平和の礎”の事を教えてくれ、伯父の名前もあるはずよーと一緒に探してくれたのです。見つけた時、その場にいる自分が途切れていた縦の線で繋がったかのような、なにかこう雷に打たれたような感覚となったのは今でも忘れられません。そしてこうして、伯父の名が一緒に刻まれていることがとてつもなくありがたかったのです。沖縄慰霊の日とはそういう広い心が根底にあるのだなと、今夜感謝の念を新たにしました。そこから流れるように続いた「花鳥風水」もまるでレクイエムのように響き、ここで短い休憩に入りました。
後半は「僕と空の間」「あかばなー」「細い三日月と満天の星」などのオリジナル曲が続きます。僕にとってはライヴでしか聴くことができない曲も多いのですが、聴くたびに違って響きます。◎ターシさんが語っていたのですがライヴで演奏する度に曲が磨かれて成長していくという事が実際にわかるような気がします。決して前回がダメだったというのではなく、回を重ねるごとに曲が魅力的になっていくのですから成長という言葉がぴったりに感じます。
そして2曲カヴァーが続いたのですが、まずは「Time After Time」。この曲はとても高いキーで歌われ、時々苦しそうに感じる事もあるのですが、今夜の声のコンディションはいつにも増して素晴らしく、続く「Can’t Help Falling in Love」は低音部から高音までもう鳥肌立つほどの美しさで、オジサンがオジサンにうっとりしちゃいました。
ここからはオリジナル曲で進みます。雪の札幌を歌った「SPK」、季節感を出そうねと「夏のモザイク」、僕にとっては初めて◎ターシさんのことを知った出会いの曲で一耳惚れした「じゅーしぃ食べたらいいさぁ」という流れに、安定の心地よさを感じます。前述のように同じ曲がセットインしても毎回違った響きをするので飽きることはありません。ソロでの弾き語りという事もあるのでしょうが、1曲1曲毎回その日だけのヴァージョンになっているかのようです。
そして「通学路」「いつも君がそばにいて」と昭和感漂う甘酸っぱい曲が並びましたが、とても好きな雰囲気です。ご本人はこういう曲は難しい、意外かもしれないけれど歌うのが恥ずかしくなると語っていましたが、聴いている昭和感満載の我々としては、その甘酸っぱい歌詞によって自分の青春時代に時間旅行へと連れて行ってもらっているような感覚になるのです。
この会場は22時には終演となっているので、あぁこれで最後だな、アンコールは無しだなとわかりやすくお客さんもそれを承知しており、それでも無理矢理1曲でも多く聴いた方がお得だというガツガツした感じがなくて好きなのですが、ちょうどあと1曲の時間となり◎ターシさんの選んだ曲は「ふくぎ」でした。これも多分毎回歌われている曲なのですが、今夜はいつもと大きく違って響きました。というのも今までこの曲の紹介のときには自宅の近くにフクギ並木があって、その実が落ちると臭いとか、それを餌にするリュウキュウオオコオモリがでかいなどという内容だったので、明るい曲だなぁくらいのイメージだったのですが、今夜の話は木を一本ずつ植えていく男の話に触れ、最初は周囲の人にバカにされていたものの何年もして大きな森になった時には人々の尊敬と感謝を集めたという昔話が大好きで、そこからの妄想でフクギの並木は各地にあるけれどあまり森はない。例えば嘉手納基地に、もし1本ずつフクギを植えていって、何年も何年もして広大な森となり、そこを歩くと遺跡のようにみんながその存在を忘れた軍の施設があったら楽しいなという思いで書いたという話を初めて聞いてからの演奏だったので、”アカズノトビラ”のような今まではどんな意味があるのだろうと思っていた、というよりも考えることさえないまま耳に入ってきていた歌詞にもその意味や整合性を見い出し、なるほどこういう内容の曲だったのかと合点がいったのです。もちろん歌詞に関してはそれぞれ聴く側がどう感じ何を思うかなのでしょうし、背景を説明されて逆に受け止め方が限定されてしまう場合もあるのですが、この曲に関してはわかった事でさらにしっかりと受け止められるようになったと思います。
こうして恒例のこのうえないLIVE!東京は終演しました。僕にとっては、◎ターシさん自身は特に想いを込めたとか、意識したということもないはずなのですが「慰霊の日」を意識し考えさせてもらえた特別なライヴになりました。そして毎回の事ながら、慌ただしい日常の生活の中で、2ヵ月に一度その音楽と歌声で肩のチカラをふっと抜いてくれるオトナの時間を持てた事に幸せを感じた夜でした。
Posted by Ken2 at
23:59
│Comments(0)
2018.6.16 タマ伸也・川畑アキラ・さとうもとき@早稲田CanColor cafe
2018年06月16日 / 川畑アキラ/ その他/ タマ伸也
2018.6.16 タマ伸也・川畑アキラ・さとうもとき ネバーエンディング3マンライブ早稲田@Music Art & Okinawa CanColor cafe

この春先に「毎月10本ライヴをやる!」と宣言し、4月から実際に「ネバーエンディングライブ」と称して全国を飛び回っているタマ伸也さん。各地でミュージシャン仲間を巻き込んでのライヴを展開しているのですが、ブログやSNSを通じて一緒にライヴしませんかと呼びかけた時に最初に呼応したのが、学生時代からの朋友でTHE TWISTARSでツインヴォーカルとしてタッグを組む川畑アキラさんだったそうで、今回はアキラさんと共に大阪、名古屋と回りいよいよ東京へ。さらに今夜は僕にとっては初めましてのさとうもときさんも加わっての同学年3マンライブとなりました。

トップ・バッターは川畑アキラさん。アキラさんのソロは久しぶりだなぁ。対バン形式のライヴだとお客さんのすべてが自分目当てで集まった訳ではなく初めて耳にする人もいるので、先ずは三線のみであいさつ代わりの「与論小唄」でスタートです。天井の高い店内に気持ち良く音が響いていきます。さらに弟さんでパーカッショニストの川畑智史さんがサポートに加わり、与論の言葉で”ようこそいらっしゃいました”を意味する「ウヮーチタバーリ」へと続きます。今まで何度も聴いた曲なのですが、今年1月にはじめて与論島を訪れたので島の風景が浮かんでとても新鮮に聴こえました。

さらに与論ベースの曲「十五夜」「島の花」とお馴染みのナンバーが続いたのですが、やはり自分と曲との距離感が縮まっている感じがしました。その曲が生まれた土地の風を肌で感じるとこんなにも受け止め方が違うものなのだなぁ。思い出したのは実際にその場所に立って眺めて距離感を掴んでから聴くアキラさんのナンバー「辺戸岬」は、それまで以上に心に共鳴するようになったという事でした。歌の背景を自分自身で感じることは僕にとってとても大きな意味を持つのだと改めて思ったのです。

「シンガーソングランナー」で盛り上がったあとはタマちゃんがステージに呼ばれ、この曲が誕生した頃のトークを交えてからの「甦る人々」です。いつ聴いてもぐっとくる曲ですが、このふたりが並んで奏でる今夜は感慨深いものがありました。

そのまま智史さんを含めて3人のセットは続き、父の日も近いという事で「親父殿よ~ウヤウムイノウタ~」を。この曲も久しぶりに生で聴くことができ、不覚にも亡き父の事をあれこれと思い出して感傷的な気持ちになると同時に、感謝でいっぱいの気持ちにさせてくれたのです。歌の持つチカラって本当にすごい!

アキラさんのセットのラストは、ひと足早く夏を運んできてくれたかのような「ティダ」で締めくくりです。3マンという事なので数曲ずつなのかなぁと思っていたら、思った以上にたっぷり聴くことができましたし、全般的に与論フレーヴァーを感じるナンバーが並びました。ふたり揃っているのだからTHE TWISTARSのナンバーも飛び出すのかなと思っていたのですが、それはやはり5人のお祭り男が集結する時にとっておいてあるのかもしれません。

短い休憩を挟んで二番手さとうもときさんの登場です。ギターを手にステージに現れたのは良い意味で昭和のシンガーの香りぷんぷんの「漢」でした。木製のステージで草履でパーカッションのようなリズムを刻みながらメッセージ色の濃い「夕焼けとテレビのニュース」で空気を一変させます。(曲名についてはもときさんのブログに掲載されていた最近のワンマンライヴのセトリを参考に歌詞からあたりをつけているので定かではありません)

正直、メッセージ性の強い曲を立て続けに聴かされたら辛いなぁと思ったのですが、ここからは自らの半生や、育って来た環境、家族などをストレートに歌い上げていく「昭和生まれのブギ」「50年」「親父と愚か者の生き方」と続き、僕よりは若いもときさんですが、歩んできた道は異なるものの同じ時代を生きてきた者として、そのひと言ひと言がまっすぐな言葉だけに尚更心に響きます。次の曲「今日また月を見ている」でも、現実に直面して挫折したり諦めたりする人も多い中、夢を見て夢を追う限り人は上を見上げて前に進み階段を上っていく事ができる、そのカッコよさを言葉と音で見せつけてくれました。

まだ出会ったばかりでそんなに親しい訳ではないのだけどと智史さんをステージに呼び、パーカッションで参加させてのラストナンバー「我は魂で世の中を耕す者なり」は大熱演で、僕を含めて半分以上のお客さんは初めてのもときさんのステージであったはずにも関わらず完全にその空気に包みこまれ、一緒に歌い、コール&レスポンスに参加です。告白すると、最初3マンライヴと知ってもときさんの名前をフライヤーで見たときに誰なんだろうこの人、出演者増やさないでいいからタマちゃんとアキラさんがたっぷり聴かせてくれればいいのにと思っていたのです。ところがこの数十分のセットのあと、財布を持ち物販に並んでいたCD全種を手にしていました。対バンのお目当て以外のアーティストにこれほど瞬間的にハマるのって年に1回あるかないかの事ですし、まして知らないアーティストのセットは酷い話ですがどうしてもニュートラルどころか、早くお目当てのバンドに替わってよというマイナスからのスタートになるので、ここまでツボに入るのは相当な事です。本来対バンの醍醐味のひとつなのでしょうが、歳を重ねて尚更新しい音楽との出会いに消極的になっている昨今は滅多にない事と言ってよいでしょう。その喜びを味あわせてくれたもときさん、すごいです!

もときさんの白熱したステージが進む中、僕の中でどんどん膨らんでいったのが”これだけ熱いパフォーマンスを繰り広げられると、トリに控える負けず嫌いのタマちゃんに火を点けるに違いない”という思いで、最後の曲でお客さんを巻き込んでの盛り上がりを呈した際にはその思いは確信に変わりました。そんなタマちゃん、ステージに登場するなり「まー、さとうもとき、おとなげない!あそこまでやる!?」と。やっぱり!そしてもときさんの最後の「我は魂で世の中を耕す者なり」がサビで”♪魂~”というリフレインで盛り上がったのをそのままコピーして、歌詞を”♪タマしんやー”に替えて歌い始めるというオープニング。どっちがおとなげないのだかで大爆笑です。その持って行きかたがさすがはタマちゃんで、そのまま「Oh! My Guitar」へと突入し、心得ているお客さんも「すぃんやっ!」のコール。冒頭の数分間で、もときさんのセットの余韻を一気にタマ伸也ワールドに塗り替えてしまいました。

フラワー・ムーヴメント時代の古き良きアメリカに想いを馳せたさわやかな「Easy Hello」でお客さんのコーラスのハモりを往年のゴダイゴのように客席でパート分けして、その一体感でがっつりと会場を掴んだあとはタマちゃんの真骨頂、誰かに入って勝手に新曲を作ってしまう”入りますシリーズ”の曲が続きます。まずは今は亡きジョン・レノンに入って書いた「LOVE & PEACE FROM 軽井沢」。最初この曲と入りますのコンセプトを聴いた時にはこの人何を言ってるのだろうと思ったものですが、繰り返し聴いているうちに自分まで入ってきてしまっているのか、徐々にジョンのメッセージのような気がしてきているから不思議です。

ここでアキラさんが呼ばれて披露されたのは、古い沖縄民謡のクレジットで見かける”作者不詳”に入って書き上げた「ゲレンの唄」で、やたらそれっぽいメロディーにアキラさんの三線が加わりさらにそれっぽくなったのですが、むしろアキラさんの”こいつ、何を唄ってんだ?”というような怪訝な表情が爆笑モノでした。

次は突然刺子半纏を羽織り、ねじり鉢巻きにSNSのフィッシングにひっかかり騙されて買っちゃったようなサングラスをかけて入ったのは吉幾三さん。そして流されたバッキング・トラックでマイク片手に熱唱したのは、その名も「娘酒」。途中、女性のお客さんに紙とマイクを渡され何かと思ったら、結婚式で父親に新婦が読む手紙でした。もう芸が細かすぎて涙が出るほど爆笑しながらもちょっとジーンとしたりして…いかいかん、完全に入ってしまっている!

アキラさん、もときさんがそれぞれ父親を歌った曲を入れたのに対し、オッサン3人が父親歌っても気持ち悪いでしょと母親の作ってくれたソウル・フードを歌った「すずこのにぎりまんま」では自分自身に入り(ってまぁそれが普通の作詞なのですがね)、ラストは憂歌団の木村充揮さんに入り書いた新曲で「やぶれかぶれの人生」です。もうこの時は逆に木村さんがタマちゃんに入ってしまったかのように歌う表情まで木村さんでした。

そしてアンコール…と思ったのですが、あまりに盛り上がり過ぎてお店で音を出してよい時間を大幅に過ぎているという事で本日はここまででとなったのですが、収まり切らない僕たちのためにアキラさんがアンプラグドでギターを弾き、3人並んでオフマイクで「今日の日はさようなら」をお客さんと一緒に大合唱という、まるでキャンプの最終日の夜に焚火を囲んでみんなで思い出を噛みしめているかのような雰囲気で、うっかり感傷的になってしまい、まずい完全に入ってしまっていると焦っているうちに終演となりました。

三人三様のステージを展開しながらも終わってみればトータルして楽しくて、色々なタイプの曲を聴くことができた夜でした。先にも書きましたが、対バンライヴと言っても大抵はお目当ての出演者以外は名前すら記憶に残らないことさえ多いのに、こうしてその日に初めて聴くアーティストのステージにも心が共鳴し気に入ってしまうのは本当に嬉しい事ですし、聴く者の個人差はあることですがセッティングの妙だと思うのです。タマちゃんがこのネバーエンディングライブを通じて、みんなを巻き込んで繋がりを広げていこうという意図を持っているとすれば、僕にとって今夜は正にそれを体現してくれたものでした。そしてもうひとつ感じたのは、楽器やマイクを置いて歩む道を変えざるを得なかった多くのミュージシャンがいる中で、こうして音楽を続けていることのカッコよさです。聴く側、ファン側のわがままもあるでしょうが、ずっと続けてくれる事がなによりの喜びなのです。
この春先に「毎月10本ライヴをやる!」と宣言し、4月から実際に「ネバーエンディングライブ」と称して全国を飛び回っているタマ伸也さん。各地でミュージシャン仲間を巻き込んでのライヴを展開しているのですが、ブログやSNSを通じて一緒にライヴしませんかと呼びかけた時に最初に呼応したのが、学生時代からの朋友でTHE TWISTARSでツインヴォーカルとしてタッグを組む川畑アキラさんだったそうで、今回はアキラさんと共に大阪、名古屋と回りいよいよ東京へ。さらに今夜は僕にとっては初めましてのさとうもときさんも加わっての同学年3マンライブとなりました。
トップ・バッターは川畑アキラさん。アキラさんのソロは久しぶりだなぁ。対バン形式のライヴだとお客さんのすべてが自分目当てで集まった訳ではなく初めて耳にする人もいるので、先ずは三線のみであいさつ代わりの「与論小唄」でスタートです。天井の高い店内に気持ち良く音が響いていきます。さらに弟さんでパーカッショニストの川畑智史さんがサポートに加わり、与論の言葉で”ようこそいらっしゃいました”を意味する「ウヮーチタバーリ」へと続きます。今まで何度も聴いた曲なのですが、今年1月にはじめて与論島を訪れたので島の風景が浮かんでとても新鮮に聴こえました。
さらに与論ベースの曲「十五夜」「島の花」とお馴染みのナンバーが続いたのですが、やはり自分と曲との距離感が縮まっている感じがしました。その曲が生まれた土地の風を肌で感じるとこんなにも受け止め方が違うものなのだなぁ。思い出したのは実際にその場所に立って眺めて距離感を掴んでから聴くアキラさんのナンバー「辺戸岬」は、それまで以上に心に共鳴するようになったという事でした。歌の背景を自分自身で感じることは僕にとってとても大きな意味を持つのだと改めて思ったのです。
「シンガーソングランナー」で盛り上がったあとはタマちゃんがステージに呼ばれ、この曲が誕生した頃のトークを交えてからの「甦る人々」です。いつ聴いてもぐっとくる曲ですが、このふたりが並んで奏でる今夜は感慨深いものがありました。
そのまま智史さんを含めて3人のセットは続き、父の日も近いという事で「親父殿よ~ウヤウムイノウタ~」を。この曲も久しぶりに生で聴くことができ、不覚にも亡き父の事をあれこれと思い出して感傷的な気持ちになると同時に、感謝でいっぱいの気持ちにさせてくれたのです。歌の持つチカラって本当にすごい!
アキラさんのセットのラストは、ひと足早く夏を運んできてくれたかのような「ティダ」で締めくくりです。3マンという事なので数曲ずつなのかなぁと思っていたら、思った以上にたっぷり聴くことができましたし、全般的に与論フレーヴァーを感じるナンバーが並びました。ふたり揃っているのだからTHE TWISTARSのナンバーも飛び出すのかなと思っていたのですが、それはやはり5人のお祭り男が集結する時にとっておいてあるのかもしれません。
短い休憩を挟んで二番手さとうもときさんの登場です。ギターを手にステージに現れたのは良い意味で昭和のシンガーの香りぷんぷんの「漢」でした。木製のステージで草履でパーカッションのようなリズムを刻みながらメッセージ色の濃い「夕焼けとテレビのニュース」で空気を一変させます。(曲名についてはもときさんのブログに掲載されていた最近のワンマンライヴのセトリを参考に歌詞からあたりをつけているので定かではありません)
正直、メッセージ性の強い曲を立て続けに聴かされたら辛いなぁと思ったのですが、ここからは自らの半生や、育って来た環境、家族などをストレートに歌い上げていく「昭和生まれのブギ」「50年」「親父と愚か者の生き方」と続き、僕よりは若いもときさんですが、歩んできた道は異なるものの同じ時代を生きてきた者として、そのひと言ひと言がまっすぐな言葉だけに尚更心に響きます。次の曲「今日また月を見ている」でも、現実に直面して挫折したり諦めたりする人も多い中、夢を見て夢を追う限り人は上を見上げて前に進み階段を上っていく事ができる、そのカッコよさを言葉と音で見せつけてくれました。
まだ出会ったばかりでそんなに親しい訳ではないのだけどと智史さんをステージに呼び、パーカッションで参加させてのラストナンバー「我は魂で世の中を耕す者なり」は大熱演で、僕を含めて半分以上のお客さんは初めてのもときさんのステージであったはずにも関わらず完全にその空気に包みこまれ、一緒に歌い、コール&レスポンスに参加です。告白すると、最初3マンライヴと知ってもときさんの名前をフライヤーで見たときに誰なんだろうこの人、出演者増やさないでいいからタマちゃんとアキラさんがたっぷり聴かせてくれればいいのにと思っていたのです。ところがこの数十分のセットのあと、財布を持ち物販に並んでいたCD全種を手にしていました。対バンのお目当て以外のアーティストにこれほど瞬間的にハマるのって年に1回あるかないかの事ですし、まして知らないアーティストのセットは酷い話ですがどうしてもニュートラルどころか、早くお目当てのバンドに替わってよというマイナスからのスタートになるので、ここまでツボに入るのは相当な事です。本来対バンの醍醐味のひとつなのでしょうが、歳を重ねて尚更新しい音楽との出会いに消極的になっている昨今は滅多にない事と言ってよいでしょう。その喜びを味あわせてくれたもときさん、すごいです!
もときさんの白熱したステージが進む中、僕の中でどんどん膨らんでいったのが”これだけ熱いパフォーマンスを繰り広げられると、トリに控える負けず嫌いのタマちゃんに火を点けるに違いない”という思いで、最後の曲でお客さんを巻き込んでの盛り上がりを呈した際にはその思いは確信に変わりました。そんなタマちゃん、ステージに登場するなり「まー、さとうもとき、おとなげない!あそこまでやる!?」と。やっぱり!そしてもときさんの最後の「我は魂で世の中を耕す者なり」がサビで”♪魂~”というリフレインで盛り上がったのをそのままコピーして、歌詞を”♪タマしんやー”に替えて歌い始めるというオープニング。どっちがおとなげないのだかで大爆笑です。その持って行きかたがさすがはタマちゃんで、そのまま「Oh! My Guitar」へと突入し、心得ているお客さんも「すぃんやっ!」のコール。冒頭の数分間で、もときさんのセットの余韻を一気にタマ伸也ワールドに塗り替えてしまいました。
フラワー・ムーヴメント時代の古き良きアメリカに想いを馳せたさわやかな「Easy Hello」でお客さんのコーラスのハモりを往年のゴダイゴのように客席でパート分けして、その一体感でがっつりと会場を掴んだあとはタマちゃんの真骨頂、誰かに入って勝手に新曲を作ってしまう”入りますシリーズ”の曲が続きます。まずは今は亡きジョン・レノンに入って書いた「LOVE & PEACE FROM 軽井沢」。最初この曲と入りますのコンセプトを聴いた時にはこの人何を言ってるのだろうと思ったものですが、繰り返し聴いているうちに自分まで入ってきてしまっているのか、徐々にジョンのメッセージのような気がしてきているから不思議です。
ここでアキラさんが呼ばれて披露されたのは、古い沖縄民謡のクレジットで見かける”作者不詳”に入って書き上げた「ゲレンの唄」で、やたらそれっぽいメロディーにアキラさんの三線が加わりさらにそれっぽくなったのですが、むしろアキラさんの”こいつ、何を唄ってんだ?”というような怪訝な表情が爆笑モノでした。
次は突然刺子半纏を羽織り、ねじり鉢巻きにSNSのフィッシングにひっかかり騙されて買っちゃったようなサングラスをかけて入ったのは吉幾三さん。そして流されたバッキング・トラックでマイク片手に熱唱したのは、その名も「娘酒」。途中、女性のお客さんに紙とマイクを渡され何かと思ったら、結婚式で父親に新婦が読む手紙でした。もう芸が細かすぎて涙が出るほど爆笑しながらもちょっとジーンとしたりして…いかいかん、完全に入ってしまっている!
アキラさん、もときさんがそれぞれ父親を歌った曲を入れたのに対し、オッサン3人が父親歌っても気持ち悪いでしょと母親の作ってくれたソウル・フードを歌った「すずこのにぎりまんま」では自分自身に入り(ってまぁそれが普通の作詞なのですがね)、ラストは憂歌団の木村充揮さんに入り書いた新曲で「やぶれかぶれの人生」です。もうこの時は逆に木村さんがタマちゃんに入ってしまったかのように歌う表情まで木村さんでした。
そしてアンコール…と思ったのですが、あまりに盛り上がり過ぎてお店で音を出してよい時間を大幅に過ぎているという事で本日はここまででとなったのですが、収まり切らない僕たちのためにアキラさんがアンプラグドでギターを弾き、3人並んでオフマイクで「今日の日はさようなら」をお客さんと一緒に大合唱という、まるでキャンプの最終日の夜に焚火を囲んでみんなで思い出を噛みしめているかのような雰囲気で、うっかり感傷的になってしまい、まずい完全に入ってしまっていると焦っているうちに終演となりました。
三人三様のステージを展開しながらも終わってみればトータルして楽しくて、色々なタイプの曲を聴くことができた夜でした。先にも書きましたが、対バンライヴと言っても大抵はお目当ての出演者以外は名前すら記憶に残らないことさえ多いのに、こうしてその日に初めて聴くアーティストのステージにも心が共鳴し気に入ってしまうのは本当に嬉しい事ですし、聴く者の個人差はあることですがセッティングの妙だと思うのです。タマちゃんがこのネバーエンディングライブを通じて、みんなを巻き込んで繋がりを広げていこうという意図を持っているとすれば、僕にとって今夜は正にそれを体現してくれたものでした。そしてもうひとつ感じたのは、楽器やマイクを置いて歩む道を変えざるを得なかった多くのミュージシャンがいる中で、こうして音楽を続けていることのカッコよさです。聴く側、ファン側のわがままもあるでしょうが、ずっと続けてくれる事がなによりの喜びなのです。
Posted by Ken2 at
23:59
│Comments(0)
2018.6.10 よなは徹@Live&Pub Shibuya gee-ge
2018年06月10日 / よなは徹
2018.6.10 よなは徹『初夏の歌会』@Live&Pub Shibuya gee-ge

沖縄の音楽にハマりはじめた頃には想像もしなかったことなのですが、東京に居ながら、いやもしかしたら東京の方が現地に居るよりも多くの沖縄ミュージシャンのライヴを聴く機会に恵まれているのです。よなは徹さんも2~3カ月に一度定期的にライヴ「ひとり歌会」を開催してくれており毎回ライヴを楽しませてもらうと同時に、民謡や古典に関してはまったく素人の僕が色々な知識を学ばせてもらったり、調べてみたい疑問を提議してもらえる嬉しい場でもあります。前回4月の歌会の際に6月にはギターの長嶺良明さん、パーカッションのカンナリさんと共にスリーピース・バンド形式でのライヴを行うと聞いて、その朗報に思わずガッツポーズをして以来この日を待ちわびていました。以前このおふたりに上地正昭さんのベースによるサンサナー・バンドを聴いた時に、何度も生音だという事を忘れるほどのタイトな演奏を聴かせてもらった事があり、今回の編成もきっと素晴らしいものになるに違いないとワクワクして今日という日を迎えたのです。

満員の客席を抜けて徹さん、良明さん、カンナリさんがステージに登場。オープニングは意表を突いてのゆったりとした舞踊曲「花笠節」でスタートです。静かに流れる曲ですが唄三線に加えアコギとパーカッションの織りなす音に幕開けからもううっとりです。カンナリさんの叩き出すシンバルの音での曲転換がかっこ良く、アップテンポな「あさどーやー(安里屋節)」へと繋がっていきます。これこれ!このアンサンブル・サウンドを待っていたのです。3人編成なのにそれを疑うほどの厚みのある音で、しかもタイトでクリアな演奏です。続く久々にセット・インした「サイサイ節」も、やはりなかなかひとりでは表現しきれないバックコーラスが入ってこそのライヴ・テイクです。

いつもの独演ライヴのように曲の解説をして進んで行くのとは違い、おなじみのナンバーを次々と繰り出していく今夜は、何か新しい事を学んで吸収するというよりも、そのサウンドに酔いしれてただただこの音空間を楽しんでゆく時間です。次はそんな場にぴったりの選曲で、草野正宗さん描き下ろしのナンバー「夜明け」です。この曲もトリオ編成でその魅力が最大限に引き出された感じです。

「激しい雨の中こんなにたくさん集まっていただき誠にありがとうございます。」というご挨拶のあと「ここで1曲ひとりでやる予定だったのですが、あまりにもスムースに進行していて時間に余裕があるので2曲やります。」と。ここまでの曲の間にMCが入るはずだったのでしょうか。むしろここまで一気に聴かせてくれたことが今宵の空気に浸らせてくれて結果的に良かったと感じました。そしてソロのコーナーはまず知名定繁さんの曲「門たんかー(じょーたんかー)」です。民謡の多くはそうなのですが、特に毛遊び系の歌は(もちろん聴き取れる訳ないので、あとから歌詞対訳をネット検索して知るのですが)その当時の生活と恋愛事情を垣間見る事ができて興味深いです。

もう1曲は「職業口説」を皮切りに沖縄の歴史的ラップ「口説」を披露。最後はリズムを変えずに弾き続け、それに乗せて松山千春さんの「大空と大地の中で」を熱唱するという、違う曲を乗せるという伝統芸をも盛り込んでくれました。僕はライヴで何度か聴かせてもらった「職業口説」が大好きで、照屋林助さんらしい笑いにあふれた歌詞が(これも後から検索して笑ったのですが)ユーモラスで、方言でない口説の部分では笑ったりしちゃったのですが、自分もそうであったように初めて聴かれる方はきちんと聴かなきゃいけないという気持ちが先行して笑いどころを聴き逃してしまっているようで、僕はすでに鍛えられているんだなぁと妙な事に感心してしまいました。

続いては3年前にリリースされた僕の大好きなアルバム「子の方(にぬふぁ)~Polaris~」の1曲目を飾る「御祝さびら」です。大好きなアルバムながら収録曲がレコ発ツアー以降はなかなかライヴで聴くことができなかったので、これは嬉しいセットインでした。これも今回のスリー・ピース編成の賜物なのでしょう。

ここで本日のスペシャル・ゲスト、護得久流民謡研究所会長であられる護得久栄昇先生の登場です。「私はずっと控室で待っていたのに、今日集まったあんたたちは誰ひとりとしてあいさつに来なかったねぇ!なんで私から挨拶をしなくてはいけないのかね!」と登場早々の上から目線全開に場内大爆笑です。「護得久流一番弟子の元ちゃんこと前川守賢くんの曲をちょこっと替え歌にしてあげたら、先生是非歌ってくださいとお願いされたから歌ってあげた曲だよ」と歌われたのは「愛さコーヒー節」です。もちろん常温です。この1曲で前半は終わりとなってしまい徹さんが「先生。時間の関係でこれで一部は終わりなんです。」と謝罪すると「何を言っているんだキミは。私は護得久栄昇だよ!私が時間に合わせるのではなく、時間が私に合わせなさい!」と徹底した上から目線キャラで爆笑の渦の中休憩に入りました。

後半も護得久先生を迎えてのセットからで、まずはお馴染みの「たーがしーじゃか」でスタートしました。お客さんも心得ていてサビでは”♪やっけーしーじゃー”の大合唱です。昨年の日比谷野音での琉球フェスティバルでもコール&レスポンスで盛り上がった曲だけに、もうすでに刷り込まれているのです。

そして「弟子のよなはくんが書いた曲で、実はよなはくんが歌うと私の10倍良いのだけど、今日は敢えて私が歌うよ!」という前置きで歌われた「汝ぐとーるむんが」と続いたのですが、いつか徹さんの声で聴いてみたいなぁと思ったのはナイショです。

ここで「護得久栄昇のシャッターチャンス・コーナー」というのがあってなんだろうと呆気にとられていたら、流されたBGMに入るシャッター音に合わせて護得久先生が決めポーズをするというコーナーで、それだけでも爆笑モノなのに後ろで徹さんが先生の鞄持ち状態で一緒にポーズを決めるものですからお腹が痛くなるほど笑わせてもらっちゃいました。

「ではここで私のデビュー曲を歌ってあげようね!」と大御所ながらデビューは遅かったのか昨年世に送り出されて衝撃を与えた「愛さ栄昇節」です。場内も“♪チャメッ!チャメッ!アッチャメー”の大合唱となり、知らない人がいきなり入ってきたら度胆を抜かれるような世界が広がっていました。これで護得久先生のコーナーは終わりでステージを降りたのですが、その時先生の顔写真Tシャツをお召しになったご婦人ファンのかたがポチ袋を渡されてたのです。「これはあれかね、所謂おひねりってやつかね。初めてのことなんで動揺するね!なんだか本物になれた気がするね!」と唐突な出来事に設定キャラが崩壊しかけてさらに再び爆笑の渦に包まれました。すかさず「ただねキミ、ゼロが一桁違うんだよ!」と慌てて軌道修正するあたりはさすがに大御所です。

3人に戻ったステージですが、この空気をいったいどうするのだろうと思っていたら徹さんがぶつけてきたのは銀座の鮨屋での出来事を曲にしたという「なごり寿司」です。これはイルカさんの「なごり雪」の替え歌で、下心満載でおねえちゃんを鮨屋に連れて行ったら、高いネタをじゃんじゃん注文した挙句、お土産を手にさっさと帰って行ってしまったという、なんとも切なくもこれまた腹を抱えて笑ってしまう嘉門達夫さんのナンバーでした。

「沖縄では旧盆が近づいてきて、あちこちからエイサーの練習の音が聴こえてきています。」という紹介からエイサーの定番曲「花の風車~スンサーミー」へ。ここでもカンナリさんのパーカッションが彩りを加えてエイサーらしい力強い響きとなっています。

そのまま続けて徹さんの十八番「唐船どーい」へ突入です。控室から護得久先生も飛び出していらして、ステージ前、通路を回ってカチャーシーを披露です。集まったお客さんも立ち上がって踊り出したい空気満載でしたが、いかんせん席の間隔が詰まっていてテーブルもあり、なかなか立ち上がる状況ではなくみなさん手だけで踊っていました。もう無条件で盛り上がるこの曲で終了です。

アンコールに応えてステージに戻ってきてくれた3人がはじめたのはアルバム「宴~party~」収録の「誇らさよ」です。スカッと抜けるメロディーラインと徹さんの速弾きが飛ばし捲くるこの曲で、なおかつ徹さんがステージを降りて通路を一周しながらの演奏を披露してくれたので今日一番の盛り上がりです。そして改めて「本当にスリーピースでの演奏なんだよね?」と確認するほどのかっこよさで、途中三線のソロから良明さんのギターのソロへと引き継がれるあたりはもう鼻血がでそうな演奏でした。

もう1曲、そしてラストに用意してくれたのは「満月の夕」です。これはもう文句なしです。ありがとう!しか浮かんできません。促すまでもなくお客さんのお囃子もバッチリ決まり素敵な一体感です。3日前に行った新良幸人さんのライヴで最後に歌われたのは「満天の星」だったのですが、徹さんの「満月の夕」とはライヴのクロージング曲として双璧を成していると思っています。良い曲、素晴らしいパフォーマンスというだけでなく、とても満ち足りた気持ちで会場を後にすることができるのです。今夜もそんな気分にさせてくれて終演です。

期待通り、いや期待を上回るライヴでしたし、短いインターバルで聴く機会のある徹さんの歌会ですが今回は明らかにここ数回のものとは内容を異にするものでした。こうして文章にしてみると、今回のセットの流れは休憩を挟んで一度途切れさせることをしないで一気に進んだ方が良かったのかもなと素人考えには思えるものでしたが、そこらへんは色々な事情があるのかもしれません。そして護得久先生のゲスト出演で更に楽しませてもらったのですが、その反面もっともっと3人のアンサンブルでたくさんの曲を、たとえば最近ごぶさたの「ありがくとぅ」あたりを聴かせてもらいたかったという思いもあります。ただ、あくまで後から振り返って思うことであって、これだけ濃厚で盛りだくさんのステージを展開してくれ、僕も他のお客さんも大満足な笑顔で会場を後にしたのですから贅沢は言えません。ひとり歌会の持つ雰囲気も大好きですが、別の楽しさを持つ今夜のようなライヴもいいなぁ。両方のセットが楽しみなところがいつも書いている通り、徹さんの抽斗の多さに他ならないことを改めて実感した『初夏の歌会』でした。
沖縄の音楽にハマりはじめた頃には想像もしなかったことなのですが、東京に居ながら、いやもしかしたら東京の方が現地に居るよりも多くの沖縄ミュージシャンのライヴを聴く機会に恵まれているのです。よなは徹さんも2~3カ月に一度定期的にライヴ「ひとり歌会」を開催してくれており毎回ライヴを楽しませてもらうと同時に、民謡や古典に関してはまったく素人の僕が色々な知識を学ばせてもらったり、調べてみたい疑問を提議してもらえる嬉しい場でもあります。前回4月の歌会の際に6月にはギターの長嶺良明さん、パーカッションのカンナリさんと共にスリーピース・バンド形式でのライヴを行うと聞いて、その朗報に思わずガッツポーズをして以来この日を待ちわびていました。以前このおふたりに上地正昭さんのベースによるサンサナー・バンドを聴いた時に、何度も生音だという事を忘れるほどのタイトな演奏を聴かせてもらった事があり、今回の編成もきっと素晴らしいものになるに違いないとワクワクして今日という日を迎えたのです。
満員の客席を抜けて徹さん、良明さん、カンナリさんがステージに登場。オープニングは意表を突いてのゆったりとした舞踊曲「花笠節」でスタートです。静かに流れる曲ですが唄三線に加えアコギとパーカッションの織りなす音に幕開けからもううっとりです。カンナリさんの叩き出すシンバルの音での曲転換がかっこ良く、アップテンポな「あさどーやー(安里屋節)」へと繋がっていきます。これこれ!このアンサンブル・サウンドを待っていたのです。3人編成なのにそれを疑うほどの厚みのある音で、しかもタイトでクリアな演奏です。続く久々にセット・インした「サイサイ節」も、やはりなかなかひとりでは表現しきれないバックコーラスが入ってこそのライヴ・テイクです。
いつもの独演ライヴのように曲の解説をして進んで行くのとは違い、おなじみのナンバーを次々と繰り出していく今夜は、何か新しい事を学んで吸収するというよりも、そのサウンドに酔いしれてただただこの音空間を楽しんでゆく時間です。次はそんな場にぴったりの選曲で、草野正宗さん描き下ろしのナンバー「夜明け」です。この曲もトリオ編成でその魅力が最大限に引き出された感じです。
「激しい雨の中こんなにたくさん集まっていただき誠にありがとうございます。」というご挨拶のあと「ここで1曲ひとりでやる予定だったのですが、あまりにもスムースに進行していて時間に余裕があるので2曲やります。」と。ここまでの曲の間にMCが入るはずだったのでしょうか。むしろここまで一気に聴かせてくれたことが今宵の空気に浸らせてくれて結果的に良かったと感じました。そしてソロのコーナーはまず知名定繁さんの曲「門たんかー(じょーたんかー)」です。民謡の多くはそうなのですが、特に毛遊び系の歌は(もちろん聴き取れる訳ないので、あとから歌詞対訳をネット検索して知るのですが)その当時の生活と恋愛事情を垣間見る事ができて興味深いです。
もう1曲は「職業口説」を皮切りに沖縄の歴史的ラップ「口説」を披露。最後はリズムを変えずに弾き続け、それに乗せて松山千春さんの「大空と大地の中で」を熱唱するという、違う曲を乗せるという伝統芸をも盛り込んでくれました。僕はライヴで何度か聴かせてもらった「職業口説」が大好きで、照屋林助さんらしい笑いにあふれた歌詞が(これも後から検索して笑ったのですが)ユーモラスで、方言でない口説の部分では笑ったりしちゃったのですが、自分もそうであったように初めて聴かれる方はきちんと聴かなきゃいけないという気持ちが先行して笑いどころを聴き逃してしまっているようで、僕はすでに鍛えられているんだなぁと妙な事に感心してしまいました。
続いては3年前にリリースされた僕の大好きなアルバム「子の方(にぬふぁ)~Polaris~」の1曲目を飾る「御祝さびら」です。大好きなアルバムながら収録曲がレコ発ツアー以降はなかなかライヴで聴くことができなかったので、これは嬉しいセットインでした。これも今回のスリー・ピース編成の賜物なのでしょう。
ここで本日のスペシャル・ゲスト、護得久流民謡研究所会長であられる護得久栄昇先生の登場です。「私はずっと控室で待っていたのに、今日集まったあんたたちは誰ひとりとしてあいさつに来なかったねぇ!なんで私から挨拶をしなくてはいけないのかね!」と登場早々の上から目線全開に場内大爆笑です。「護得久流一番弟子の元ちゃんこと前川守賢くんの曲をちょこっと替え歌にしてあげたら、先生是非歌ってくださいとお願いされたから歌ってあげた曲だよ」と歌われたのは「愛さコーヒー節」です。もちろん常温です。この1曲で前半は終わりとなってしまい徹さんが「先生。時間の関係でこれで一部は終わりなんです。」と謝罪すると「何を言っているんだキミは。私は護得久栄昇だよ!私が時間に合わせるのではなく、時間が私に合わせなさい!」と徹底した上から目線キャラで爆笑の渦の中休憩に入りました。
後半も護得久先生を迎えてのセットからで、まずはお馴染みの「たーがしーじゃか」でスタートしました。お客さんも心得ていてサビでは”♪やっけーしーじゃー”の大合唱です。昨年の日比谷野音での琉球フェスティバルでもコール&レスポンスで盛り上がった曲だけに、もうすでに刷り込まれているのです。
そして「弟子のよなはくんが書いた曲で、実はよなはくんが歌うと私の10倍良いのだけど、今日は敢えて私が歌うよ!」という前置きで歌われた「汝ぐとーるむんが」と続いたのですが、いつか徹さんの声で聴いてみたいなぁと思ったのはナイショです。
ここで「護得久栄昇のシャッターチャンス・コーナー」というのがあってなんだろうと呆気にとられていたら、流されたBGMに入るシャッター音に合わせて護得久先生が決めポーズをするというコーナーで、それだけでも爆笑モノなのに後ろで徹さんが先生の鞄持ち状態で一緒にポーズを決めるものですからお腹が痛くなるほど笑わせてもらっちゃいました。
「ではここで私のデビュー曲を歌ってあげようね!」と大御所ながらデビューは遅かったのか昨年世に送り出されて衝撃を与えた「愛さ栄昇節」です。場内も“♪チャメッ!チャメッ!アッチャメー”の大合唱となり、知らない人がいきなり入ってきたら度胆を抜かれるような世界が広がっていました。これで護得久先生のコーナーは終わりでステージを降りたのですが、その時先生の顔写真Tシャツをお召しになったご婦人ファンのかたがポチ袋を渡されてたのです。「これはあれかね、所謂おひねりってやつかね。初めてのことなんで動揺するね!なんだか本物になれた気がするね!」と唐突な出来事に設定キャラが崩壊しかけてさらに再び爆笑の渦に包まれました。すかさず「ただねキミ、ゼロが一桁違うんだよ!」と慌てて軌道修正するあたりはさすがに大御所です。
3人に戻ったステージですが、この空気をいったいどうするのだろうと思っていたら徹さんがぶつけてきたのは銀座の鮨屋での出来事を曲にしたという「なごり寿司」です。これはイルカさんの「なごり雪」の替え歌で、下心満載でおねえちゃんを鮨屋に連れて行ったら、高いネタをじゃんじゃん注文した挙句、お土産を手にさっさと帰って行ってしまったという、なんとも切なくもこれまた腹を抱えて笑ってしまう嘉門達夫さんのナンバーでした。
「沖縄では旧盆が近づいてきて、あちこちからエイサーの練習の音が聴こえてきています。」という紹介からエイサーの定番曲「花の風車~スンサーミー」へ。ここでもカンナリさんのパーカッションが彩りを加えてエイサーらしい力強い響きとなっています。
そのまま続けて徹さんの十八番「唐船どーい」へ突入です。控室から護得久先生も飛び出していらして、ステージ前、通路を回ってカチャーシーを披露です。集まったお客さんも立ち上がって踊り出したい空気満載でしたが、いかんせん席の間隔が詰まっていてテーブルもあり、なかなか立ち上がる状況ではなくみなさん手だけで踊っていました。もう無条件で盛り上がるこの曲で終了です。
アンコールに応えてステージに戻ってきてくれた3人がはじめたのはアルバム「宴~party~」収録の「誇らさよ」です。スカッと抜けるメロディーラインと徹さんの速弾きが飛ばし捲くるこの曲で、なおかつ徹さんがステージを降りて通路を一周しながらの演奏を披露してくれたので今日一番の盛り上がりです。そして改めて「本当にスリーピースでの演奏なんだよね?」と確認するほどのかっこよさで、途中三線のソロから良明さんのギターのソロへと引き継がれるあたりはもう鼻血がでそうな演奏でした。
もう1曲、そしてラストに用意してくれたのは「満月の夕」です。これはもう文句なしです。ありがとう!しか浮かんできません。促すまでもなくお客さんのお囃子もバッチリ決まり素敵な一体感です。3日前に行った新良幸人さんのライヴで最後に歌われたのは「満天の星」だったのですが、徹さんの「満月の夕」とはライヴのクロージング曲として双璧を成していると思っています。良い曲、素晴らしいパフォーマンスというだけでなく、とても満ち足りた気持ちで会場を後にすることができるのです。今夜もそんな気分にさせてくれて終演です。
期待通り、いや期待を上回るライヴでしたし、短いインターバルで聴く機会のある徹さんの歌会ですが今回は明らかにここ数回のものとは内容を異にするものでした。こうして文章にしてみると、今回のセットの流れは休憩を挟んで一度途切れさせることをしないで一気に進んだ方が良かったのかもなと素人考えには思えるものでしたが、そこらへんは色々な事情があるのかもしれません。そして護得久先生のゲスト出演で更に楽しませてもらったのですが、その反面もっともっと3人のアンサンブルでたくさんの曲を、たとえば最近ごぶさたの「ありがくとぅ」あたりを聴かせてもらいたかったという思いもあります。ただ、あくまで後から振り返って思うことであって、これだけ濃厚で盛りだくさんのステージを展開してくれ、僕も他のお客さんも大満足な笑顔で会場を後にしたのですから贅沢は言えません。ひとり歌会の持つ雰囲気も大好きですが、別の楽しさを持つ今夜のようなライヴもいいなぁ。両方のセットが楽しみなところがいつも書いている通り、徹さんの抽斗の多さに他ならないことを改めて実感した『初夏の歌会』でした。
Posted by Ken2 at
23:59
│Comments(0)
2018.6.7 新良幸人@Live & Shot.Bar タルマッシュ
2018年06月07日 / 新良幸人
2018.6.7 新良幸人@Live & Shot.Bar タルマッシュ

東京から1950km離れた石垣島を中心とした八重山諸島。僕が沖縄の音楽と出会いのめり込んでいった原点の場所です。この2週間に期せずして竹富島、石垣島のミュージシャンの方々のライヴが続き、まるで「八重山祭り」の様相を呈していますが、今夜はその最終日。ズブズブのめり込ませていった張本人、新良幸人さんのライヴです。大袈裟に言えば、この人の唄三線に出会わなかったら今の僕の人生は大きく変わっていたというほどの存在。そんな幸人さんのライヴ、考えてみたら半年ぶりで今年初めてです。「鷲の鳥」はとうに大空に飛び去り、既に「うりずん」の季節も過ぎてしまいましたが、今夜はどんな世界に連れて行ってもらえるのか期待に胸を高鳴らせて西大井に向かいました。会場はいつもながらの満席で開演前から静かな熱気に包まれています。
店内の照明が落とされみんなが注視するドアから入って来た幸人さんは白地に真紅の薔薇の花が染め抜かれたシャツ姿で登場。僕が着たらド派手な高島屋の包装紙のようになってしまうような服ですが、幸人さんは違和感なく着こなしてしまうあたり流石スーパースターです。颯爽と三線のストラップを掛けて奏で始めると、その音色で僕たちをいざない、八重山の空気へと瞬間移動で導いてくれているかのようでした。そして降り立った地は白保の浜でオープニングは「ファムレウタ」です。いきなりこれを持ってこられたらそれはもうメロメロです。子守唄であるこの曲は文字通り気持ちを落ち着かせてくれて、眠りこそはしませんが時の流れが切り替わるのを感じさせてくれます。
「東京も梅雨入りしてしまいましたが、さすがは持っている僕です。雨の予報も跳ね除けて気持ち良い天気となりました。お足元のよろしい中お集まりいただきましてありがとうございます。」というご挨拶のあと「もう季節は過ぎてしまいましたが」とゆったりとしたテンポで始まったのは、この季節にライヴで聴かせてもらえるのを楽しみにしているお気に入りのナンバー「うりずんの詩」です。冬が終わり夏の暑さがやってくるまでの短くも心地よい季節を歌った曲で、特にその風を表す「やふぁやふぁ」という言葉の響きがとても素敵です。この曲の途中に「大岳の~」で始まる民謡がインサートされていましたが小浜島のものなのかな。とてもいい具合に繋がっていました。
続いてはカラ岳の話から白保の隣の集落の「桃里節」で、この曲のお囃子は「ヨーサティヨー ヒーヨーンナ」と入るのですが、幸人さんの解説では桃里村ではきれいな花がたくさん咲いているけどおねえちゃんは年中きれいに咲いているのよーって歌詞なので勘違いしている人がいて、このお囃子を「よーサチヨ いい女」だと思っていると。場内大爆笑で「全国のサチヨさんに捧げます」と歌い始め、実際途中お囃子の歌詞を「よーサチヨ いい女」に変えて更に盛り上げます。いつもは「俺のペースでやらせて!」と手拍子を止めたりする幸人さんですが、今夜はむしろ手拍子を促したり、お囃子をコール&レスポンス的に歌わせてくれたりと大違い。この場所のお客さんを信頼している上によほど心地よかったのかな。楽しい流れで進んでいきました。

<資料画像>
幸人さんの唄三線による八重山ツアーは石垣島から西表島へと移動して「まるまぶんさん」そして「殿様節」へと続きます。恒例の池田卓さんイジリもなく進んで行きました。僕はまだ訪れた事のない島なのですが、ライヴでおなじみのこの2曲を聴くといつもまだ見ぬ島の風景に思いを馳せてしまいます。ツアーは石垣の離島ターミナルを経由する事もなく今度は黒島へ。島のモテモテ好色じいさんを歌ったという「山崎ぬアブジャーマ」という曲なのですが、歌詞の意味はさっぱりわからなくても解説してもらえてイメージが湧き、とてもユーモラスに聴こえました。第一部の最後にツアーは一気に沖縄本島へ。たしか、ゆいレールの牧志駅到着の時に車内で流れる「いちゅび小節」です。いちゅびとはイチゴ、系で言えば野いちごの事で、想いを寄せる人の事を「いちごちゃん」と呼んでいたそうです。要は「いちごちゃんキターーっ!萌えーーーっ!」みたいな内容の歌で、時代は変われどもラヴソングは王道なのだなぁとニマニマ聴いてしまいました。饒舌さも加わり1時間越えの前半ステージをたっぷりと堪能させてくれて休憩に突入です。

ダーク・カラーのシャツにお色直しをして登場した後半は、いきなりParsha cluBのナンバー「五穀豊穣」でスタートです。お客さんも「イヤササ!」のお囃子を入れて盛り上がり、幸人さんも楽しそうです。今夜の一発目が「ファムレウタ」だった事もびっくりでしたが、後半も驚きのスタートです。そしてもちろんのこと早くParshaのライヴが見たくなりました。続いては「ここでTHE SAKISHIMA meetingのナンバーをひとつ。いつもは相方の下地イサムと一緒にやっているのだけど、ひとりでできるかなぁ。」と唄三線で披露されたのは「島風」です。TSmのヴァージョンとはひと味違った島風が吹き渡り、これはこれでいいなぁと思いました。
ここで突然「ハナミズキ」のメロディを奏で始めた幸人さん。みんながびっくりしているのに気をよくしたのか「じゃあ、絶対やらないシリーズ!」と弾き始めたのは、なんとBEGINのお馴染みのナンバー。イントロが終わるとシャツのボタンを外して「♪これが島人の身体~」とのオチに大爆笑。更にメロディは「童神」へと進み、乗って来たお客さんが歌い始めると「そういうコーナーじゃないからっ!」と制されて再び大爆笑の渦となりました。この流れからどこに持って行くのかと思っていたら、始まったイントロは僕にとってParsha cluBの至高のナンバーのひとつで、27年前にこの曲があったら絶対に結婚式で流したかったラヴソング「かながな」です。ただこの愛のカタチは、ある程度人生を共に歩んで来たからこそ感じられるものなのかもしれないなぁ。歌詞もメロディも本当に美しいこの曲、もうただただうっとりと聴き惚れてしまいました。
次は「春になると大きな蝶々と小さな蝶々が…」でお馴染みの「綾蝶」の歌詞がニュー・ヴァージョンのちょっとエロい口上で紹介されてのスタートです。続いてParshaのナンバーで「夏ぬ恋」を三線一棹で歌いあげます。どちらが良いとか言う事ではなく、バンドとしてのアンサンブルで慣れている曲も、こうしてゆったりと唄三線で聴くのも切なさが増していい感じです。
ここからライヴで定番の民謡「加那よ」「天川」と続いたのですが、もちろん幸人さんならではのアレンジが施されていて、歌い終わったあとに「俺はいつも解体してやっているんだけど、元はこんな感じね。」と所謂工工四に忠実に少し演奏してくれて、いつのまにか幸人さんヴァージョンにすっかり馴染んでいましたがその違いを改めて教えてくれました。続いては幸人さんがかなり若い時に書かれた曲で、Parsha cluBのファースト・アルバムに収録されている「風ゆイヤリ」です。この曲も今夜は手拍子を止められる事もなく、中途半端に止めてしまうと最後の横笛の音色が聴かれなくなってしまうので、フルコーラスリズムを崩さないようにキープです。その甲斐あって幻想的な笛の音も聴くことができた上「なんだかみんなで一緒にやっている感があって、こういうのもいいね!」とお褒めの言葉を頂いたほどです。本当に今夜はどうしちゃったのでしょう。でもファンにしてみればとても嬉しいことです。
最後になにを持ってくるのかなぁと思っていたらサトウユウコさんとのユニット・アルバムのタイトル・トラック「浄夜」を入れてくれました。静かに音が紡がれていきながら、とても広大な広がりを持っているこの曲ですが、ユウコさんのピアノ無しの唄三線のみでも十分にその風景を描いてくれ、曲の持つチカラさえ伝わってきます。こうして今夜セット・インした曲を見るとすごいなぁ。幸人さんの活動を全般カヴァーしていてキャリア・ベスト盤のような選曲です。ここまで来たらアンコールは変化球は避けて直球でいって欲しいと願ったらその思いが通じ、鉄板曲「満天の星」で結んでくれました。鉄板曲ですからサプライズはないのですが、やはりこの曲が無いのは淋し過ぎます。幸人さんのライヴに行った回数この曲は聴きたいのです。今夜もその唄三線でさんざめく天河を僕の視界いっぱいに描き出してくれました。

楽しかった、満ち足りた、心に染みたなど色々な表現がありますが、それらをすべてひっくるめた上で、その音楽で、ライヴという限られた時間でこれほど僕に幸せを感じさせてくれる人はそうそういません。(あ!だから「幸」「人」さんなのか!!)それも三線と歌声だけでこんなにも惹きつけてくれるのですからその力量は半端ないです。そして印象的だったのは「加那よ」の時に語っていた「解体」という言葉です。きっと権威と呼ばれる偉い方たちは基本通りでない事を快く思っていないこともあるのは想像がつきます。基本に忠実に!みたいな頭の固さがあるのでしょう。ただ、出来ないから自分のできる方法で表現しているのではなく、やれと言われるならできますよというしっかりとした基礎を身につけた上での「解体」なのですから、その先には” reconstruction”すなわち「復興」があると思うのです。僕としてはそれは素晴らしい事だと思うのです。実際両方を聴いてこうして「解体」されたサウンドにハマっていく者もいるのですから。そんな事を思いつつ見えるはずのない天の川の下をニマニマしながら家路についたのは、ほぼ23時。東京で、金曜でも土曜でもない夜のライヴ終演時間としては異例です。それだけ幸人さんも楽しんだライヴだったのだろうなぁ。そう思いたいです。

東京から1950km離れた石垣島を中心とした八重山諸島。僕が沖縄の音楽と出会いのめり込んでいった原点の場所です。この2週間に期せずして竹富島、石垣島のミュージシャンの方々のライヴが続き、まるで「八重山祭り」の様相を呈していますが、今夜はその最終日。ズブズブのめり込ませていった張本人、新良幸人さんのライヴです。大袈裟に言えば、この人の唄三線に出会わなかったら今の僕の人生は大きく変わっていたというほどの存在。そんな幸人さんのライヴ、考えてみたら半年ぶりで今年初めてです。「鷲の鳥」はとうに大空に飛び去り、既に「うりずん」の季節も過ぎてしまいましたが、今夜はどんな世界に連れて行ってもらえるのか期待に胸を高鳴らせて西大井に向かいました。会場はいつもながらの満席で開演前から静かな熱気に包まれています。
店内の照明が落とされみんなが注視するドアから入って来た幸人さんは白地に真紅の薔薇の花が染め抜かれたシャツ姿で登場。僕が着たらド派手な高島屋の包装紙のようになってしまうような服ですが、幸人さんは違和感なく着こなしてしまうあたり流石スーパースターです。颯爽と三線のストラップを掛けて奏で始めると、その音色で僕たちをいざない、八重山の空気へと瞬間移動で導いてくれているかのようでした。そして降り立った地は白保の浜でオープニングは「ファムレウタ」です。いきなりこれを持ってこられたらそれはもうメロメロです。子守唄であるこの曲は文字通り気持ちを落ち着かせてくれて、眠りこそはしませんが時の流れが切り替わるのを感じさせてくれます。
「東京も梅雨入りしてしまいましたが、さすがは持っている僕です。雨の予報も跳ね除けて気持ち良い天気となりました。お足元のよろしい中お集まりいただきましてありがとうございます。」というご挨拶のあと「もう季節は過ぎてしまいましたが」とゆったりとしたテンポで始まったのは、この季節にライヴで聴かせてもらえるのを楽しみにしているお気に入りのナンバー「うりずんの詩」です。冬が終わり夏の暑さがやってくるまでの短くも心地よい季節を歌った曲で、特にその風を表す「やふぁやふぁ」という言葉の響きがとても素敵です。この曲の途中に「大岳の~」で始まる民謡がインサートされていましたが小浜島のものなのかな。とてもいい具合に繋がっていました。
続いてはカラ岳の話から白保の隣の集落の「桃里節」で、この曲のお囃子は「ヨーサティヨー ヒーヨーンナ」と入るのですが、幸人さんの解説では桃里村ではきれいな花がたくさん咲いているけどおねえちゃんは年中きれいに咲いているのよーって歌詞なので勘違いしている人がいて、このお囃子を「よーサチヨ いい女」だと思っていると。場内大爆笑で「全国のサチヨさんに捧げます」と歌い始め、実際途中お囃子の歌詞を「よーサチヨ いい女」に変えて更に盛り上げます。いつもは「俺のペースでやらせて!」と手拍子を止めたりする幸人さんですが、今夜はむしろ手拍子を促したり、お囃子をコール&レスポンス的に歌わせてくれたりと大違い。この場所のお客さんを信頼している上によほど心地よかったのかな。楽しい流れで進んでいきました。

<資料画像>
幸人さんの唄三線による八重山ツアーは石垣島から西表島へと移動して「まるまぶんさん」そして「殿様節」へと続きます。恒例の池田卓さんイジリもなく進んで行きました。僕はまだ訪れた事のない島なのですが、ライヴでおなじみのこの2曲を聴くといつもまだ見ぬ島の風景に思いを馳せてしまいます。ツアーは石垣の離島ターミナルを経由する事もなく今度は黒島へ。島のモテモテ好色じいさんを歌ったという「山崎ぬアブジャーマ」という曲なのですが、歌詞の意味はさっぱりわからなくても解説してもらえてイメージが湧き、とてもユーモラスに聴こえました。第一部の最後にツアーは一気に沖縄本島へ。たしか、ゆいレールの牧志駅到着の時に車内で流れる「いちゅび小節」です。いちゅびとはイチゴ、系で言えば野いちごの事で、想いを寄せる人の事を「いちごちゃん」と呼んでいたそうです。要は「いちごちゃんキターーっ!萌えーーーっ!」みたいな内容の歌で、時代は変われどもラヴソングは王道なのだなぁとニマニマ聴いてしまいました。饒舌さも加わり1時間越えの前半ステージをたっぷりと堪能させてくれて休憩に突入です。

ダーク・カラーのシャツにお色直しをして登場した後半は、いきなりParsha cluBのナンバー「五穀豊穣」でスタートです。お客さんも「イヤササ!」のお囃子を入れて盛り上がり、幸人さんも楽しそうです。今夜の一発目が「ファムレウタ」だった事もびっくりでしたが、後半も驚きのスタートです。そしてもちろんのこと早くParshaのライヴが見たくなりました。続いては「ここでTHE SAKISHIMA meetingのナンバーをひとつ。いつもは相方の下地イサムと一緒にやっているのだけど、ひとりでできるかなぁ。」と唄三線で披露されたのは「島風」です。TSmのヴァージョンとはひと味違った島風が吹き渡り、これはこれでいいなぁと思いました。
ここで突然「ハナミズキ」のメロディを奏で始めた幸人さん。みんながびっくりしているのに気をよくしたのか「じゃあ、絶対やらないシリーズ!」と弾き始めたのは、なんとBEGINのお馴染みのナンバー。イントロが終わるとシャツのボタンを外して「♪これが島人の身体~」とのオチに大爆笑。更にメロディは「童神」へと進み、乗って来たお客さんが歌い始めると「そういうコーナーじゃないからっ!」と制されて再び大爆笑の渦となりました。この流れからどこに持って行くのかと思っていたら、始まったイントロは僕にとってParsha cluBの至高のナンバーのひとつで、27年前にこの曲があったら絶対に結婚式で流したかったラヴソング「かながな」です。ただこの愛のカタチは、ある程度人生を共に歩んで来たからこそ感じられるものなのかもしれないなぁ。歌詞もメロディも本当に美しいこの曲、もうただただうっとりと聴き惚れてしまいました。
次は「春になると大きな蝶々と小さな蝶々が…」でお馴染みの「綾蝶」の歌詞がニュー・ヴァージョンのちょっとエロい口上で紹介されてのスタートです。続いてParshaのナンバーで「夏ぬ恋」を三線一棹で歌いあげます。どちらが良いとか言う事ではなく、バンドとしてのアンサンブルで慣れている曲も、こうしてゆったりと唄三線で聴くのも切なさが増していい感じです。
ここからライヴで定番の民謡「加那よ」「天川」と続いたのですが、もちろん幸人さんならではのアレンジが施されていて、歌い終わったあとに「俺はいつも解体してやっているんだけど、元はこんな感じね。」と所謂工工四に忠実に少し演奏してくれて、いつのまにか幸人さんヴァージョンにすっかり馴染んでいましたがその違いを改めて教えてくれました。続いては幸人さんがかなり若い時に書かれた曲で、Parsha cluBのファースト・アルバムに収録されている「風ゆイヤリ」です。この曲も今夜は手拍子を止められる事もなく、中途半端に止めてしまうと最後の横笛の音色が聴かれなくなってしまうので、フルコーラスリズムを崩さないようにキープです。その甲斐あって幻想的な笛の音も聴くことができた上「なんだかみんなで一緒にやっている感があって、こういうのもいいね!」とお褒めの言葉を頂いたほどです。本当に今夜はどうしちゃったのでしょう。でもファンにしてみればとても嬉しいことです。
最後になにを持ってくるのかなぁと思っていたらサトウユウコさんとのユニット・アルバムのタイトル・トラック「浄夜」を入れてくれました。静かに音が紡がれていきながら、とても広大な広がりを持っているこの曲ですが、ユウコさんのピアノ無しの唄三線のみでも十分にその風景を描いてくれ、曲の持つチカラさえ伝わってきます。こうして今夜セット・インした曲を見るとすごいなぁ。幸人さんの活動を全般カヴァーしていてキャリア・ベスト盤のような選曲です。ここまで来たらアンコールは変化球は避けて直球でいって欲しいと願ったらその思いが通じ、鉄板曲「満天の星」で結んでくれました。鉄板曲ですからサプライズはないのですが、やはりこの曲が無いのは淋し過ぎます。幸人さんのライヴに行った回数この曲は聴きたいのです。今夜もその唄三線でさんざめく天河を僕の視界いっぱいに描き出してくれました。

楽しかった、満ち足りた、心に染みたなど色々な表現がありますが、それらをすべてひっくるめた上で、その音楽で、ライヴという限られた時間でこれほど僕に幸せを感じさせてくれる人はそうそういません。(あ!だから「幸」「人」さんなのか!!)それも三線と歌声だけでこんなにも惹きつけてくれるのですからその力量は半端ないです。そして印象的だったのは「加那よ」の時に語っていた「解体」という言葉です。きっと権威と呼ばれる偉い方たちは基本通りでない事を快く思っていないこともあるのは想像がつきます。基本に忠実に!みたいな頭の固さがあるのでしょう。ただ、出来ないから自分のできる方法で表現しているのではなく、やれと言われるならできますよというしっかりとした基礎を身につけた上での「解体」なのですから、その先には” reconstruction”すなわち「復興」があると思うのです。僕としてはそれは素晴らしい事だと思うのです。実際両方を聴いてこうして「解体」されたサウンドにハマっていく者もいるのですから。そんな事を思いつつ見えるはずのない天の川の下をニマニマしながら家路についたのは、ほぼ23時。東京で、金曜でも土曜でもない夜のライヴ終演時間としては異例です。それだけ幸人さんも楽しんだライヴだったのだろうなぁ。そう思いたいです。
Posted by Ken2 at
23:59
│Comments(0)
2018.6.2 石垣よしゆき@新大久保・沖縄島唄カーニバル
2018年06月02日 / 石垣喜幸
2018.6.2 石垣よしゆき アコースティック音夜祭 -オンヤサイ- 東京2DAYS SPECIAL@新大久保・沖縄島唄カーニバル

昨夜の「白百合の宴」でその歌声に酔いしれたもーちゃんこと石垣よしゆきさん。今宵は一昨日の小岩こだまでのライヴと合わせてのアコースティック音夜祭 -オンヤサイ- 東京2DAYS SPECIALの2日目で、東京では半年ぶりのワンマン・ライヴです。ゲストに昨夜もサポートされた波照間剛さんを迎えてのステージとの事で、パーカッションが加わりよりパワフルなライヴに期待が高まります。

第一部はもーちゃんひとりでのセットです。この3月にリリースされた文字通り自主制作のCD「あいのうた」に収録されている「悲しみのない世界」でスタートです。この曲はもーちゃんの真骨頂とも言える優しく寄り添って肩を抱き包み込んでくれるような詩とメロディーの曲で、それは力強い言葉で背中を押される応援歌とは違い、ありのままの自分を認めさせてくれるような包容力を持っているのです。もうこのオープニングと続いて演奏された曲でもーちゃんの世界に空間移動したような状態です。

軽妙なトークを挟んで紹介された次の曲は、20年ほど前に書いて一度ライヴで歌ったものの、まだこの曲を歌うのは自分には早いと封印し最近ようやく歌っても良いと感じるようになりセットインするようになったという「春の子守唄」で、亡くなられたおばあさんの事を歌った曲だそうです。自分で作った歌ながら、歌い方なり技量なりが自ら納得できずに封印するって、自分の作品に対するある意味責任感なのかもしれません。その曲に対する誠実さにとても共感を覚えます。

もーちゃんの曲を聴くとなぜかケルト音楽の持つ世界観を感じるのですが、そんなフレーヴァーの色濃い「光」「タイムトラベル」と続きます。世界観という表現はあくまで感覚なものなのですが、決してケルティックサウンドをパクっているというのではなく、その根底に流れているスピリチュアルな部分に同じものを感じるのです。特に最近何度かライヴで聴く機会のある三拍子の「タイムトラベル」にはそれを強く感じて大好きなナンバーです。この曲も早く音源化して欲しいなぁと思っています。

「ここでカヴァーをやろうか」と歌い始めたのはなんとジュリーの「時の過ぎゆくままに」でびっくりしたのですが、これがなんとももーちゃんの声にぴったりとハマっていて聴き惚れてしまいました。さらにカヴァーは続きこれまたびっくりの「男はつらいよ」です。そう、寅さんの主題歌です。これまたすっかりもーちゃんのオリジナル曲であるかのように自分のものにしていました。歌の途中に「わたくし、生まれも育ちも沖縄県石垣市登野城7丁目・・・」という寅さんの口上から始まるトークが挟まり、そこではずっと謎でありながら聞くに聞けなかったなぜ「もーちゃん」というニックネームなのかという疑問に対する答えが解明されました。

第一部の最後にここ何回かのライヴに鍵盤でサポートしている後輩の高嶺史さんが呼び込まれピアニカで参加して歌われたのは、もーちゃんのデビュー曲「見上げれば」です。この曲が震災後にラジオで流されていたことをきっかけに宮城県石巻と繋がったもーちゃんが、今年3月11日にその石巻でライヴを行いその会場に響いて震えたこの曲が、今宵は東京の会場で響き、さらにそこにはその石巻のライヴでお会いした主催された方も駆けつけて来ていらしており、僕の視界には彼女ともーちゃんが一緒に収まっていて得も言われぬ感慨に包まれました。

休憩明けは恒例のじゃんけん大会で石垣からのおみやげ争奪戦で盛り上がり、そこから始まった第二部はいよいよ島の先輩パーカッショニスト波照間剛さんを迎えてのセットです。いきなり「永久の夢」でもう休憩がなかったかのように一気にヴォルテージがマックスに昇りつめました。めちゃめちゃかっこいい曲なのですが、やはりパーカッションが入るとより一層高揚感が増します。続く「10年」もゆったり流れるような曲ながら波照間さんの叩き出す音が曲全体をクッキリと鮮やかにしている感じで、そうそうこれだよね!という心持ちでその音に身を任せました。

ここで昨夜の「白百合の宴」でも共演された石井幸枝さんがステージに呼ばれフルートを手に登場し、トリオ編成による「呼吸」をブルージィに演奏です。ジャズクラブで強めのお酒を手に聴いているような雰囲気で素敵です。

幸枝さんに替わっては、いい感じに出来上がりつつある高嶺さんが再び呼ばれ、ピアニカで参加しての「都バス」、そして「あいのうた」に収録されている「中央線」と明るく楽しいナンバーが続きます。先輩と後輩とのトリオ編成にもーちゃんも楽しそうです。

このまま盛り上がって終盤を終えるのかと思いきや、意表を突いて突然のカヴァー曲、それも「天城越え」です。もう完全にもーちゃんのレパートリーとなっているだけにコブシの入り方もぞくぞくするほどです。このような情歌も自分のものにしてしまう歌唱力はすごいと敬服しちゃいますし、何の曲だかわかったところでお客さんからは笑いが漏れるのですが、進んで行くうちに決してお遊びで歌ってみましたという感じではなく、引き込んでいってしまうのはさすがもーちゃんです。

ラストは、そうだこの曲がまだでしたという名曲「こだま」。歌詞のひとつひとつがきっちりと届いて響いてくるこの曲に今宵も涙腺崩壊寸前でしたし、実際に目頭を拭っている何人かのお客さんもステージ横の僕の席からは視界の端に見えていてもらい泣きしそうになりました。これだけ心を揺さぶる曲をこうして、今回は2夜連続で聴く事ができたのは、まるで僕の奥深くにある土壌に水を撒いてもらったかのようでした。

アンコールは再び高嶺さんが呼ばれ更に気持ちよくなった状態で登場。もーちゃんが梅雨入りしたはずの沖縄が灼熱の暑さという話をしている時に謎のメロディーをピアニカで奏でていて何かと思ったら「梅雨入りを音で表わしてみました」ということで場内爆笑です。このトリオでノリノリなナンバー「海へ行こう」が始まり、お客さんもコーラスで参加しての一体感です。

そしてもう1曲はアルバムのタイトルトラックである文字通りのラヴソング「愛のうた」です。ただこの曲もいわゆる君が好きだI LOVE YOUというだけの想いではなく、歌われている「君」は性別も年齢も関係なくそれぞれに対する形の「愛」を伝え届けてくれているように感じるのは、やはりもーちゃんの声と感性の持つ包容力なのでしょう。それがこんなおじさんの僕にさえ伝わってくる、届いてくるのですから、そのチカラは半端ないことは間違いありません。

こうして幕を閉じた今回の音夜祭も、時季はずれますが石垣からさわやかなうりずんの風を吹かせてくれたかのような時間でした。以前のライヴタイトルで自分の名前を織り込んで「喜幸哀楽」と名付けられていたものがありましたが、今夜のライヴのあとにその言葉を思い出しました。2時間ちょっとのライヴの中には確かに「喜び」「幸せ」「哀しみ」「楽しさ」のすべてが含まれていて、どの気持ちも素直に出していいんだよと歌を通して語りかけてくれているかのようです。本当にもーちゃん、石垣よしゆきさんの歌声はその文字の通り「喜び」と「幸せ」をもたらしてくれるのです。

昨夜の「白百合の宴」でその歌声に酔いしれたもーちゃんこと石垣よしゆきさん。今宵は一昨日の小岩こだまでのライヴと合わせてのアコースティック音夜祭 -オンヤサイ- 東京2DAYS SPECIALの2日目で、東京では半年ぶりのワンマン・ライヴです。ゲストに昨夜もサポートされた波照間剛さんを迎えてのステージとの事で、パーカッションが加わりよりパワフルなライヴに期待が高まります。
第一部はもーちゃんひとりでのセットです。この3月にリリースされた文字通り自主制作のCD「あいのうた」に収録されている「悲しみのない世界」でスタートです。この曲はもーちゃんの真骨頂とも言える優しく寄り添って肩を抱き包み込んでくれるような詩とメロディーの曲で、それは力強い言葉で背中を押される応援歌とは違い、ありのままの自分を認めさせてくれるような包容力を持っているのです。もうこのオープニングと続いて演奏された曲でもーちゃんの世界に空間移動したような状態です。
軽妙なトークを挟んで紹介された次の曲は、20年ほど前に書いて一度ライヴで歌ったものの、まだこの曲を歌うのは自分には早いと封印し最近ようやく歌っても良いと感じるようになりセットインするようになったという「春の子守唄」で、亡くなられたおばあさんの事を歌った曲だそうです。自分で作った歌ながら、歌い方なり技量なりが自ら納得できずに封印するって、自分の作品に対するある意味責任感なのかもしれません。その曲に対する誠実さにとても共感を覚えます。
もーちゃんの曲を聴くとなぜかケルト音楽の持つ世界観を感じるのですが、そんなフレーヴァーの色濃い「光」「タイムトラベル」と続きます。世界観という表現はあくまで感覚なものなのですが、決してケルティックサウンドをパクっているというのではなく、その根底に流れているスピリチュアルな部分に同じものを感じるのです。特に最近何度かライヴで聴く機会のある三拍子の「タイムトラベル」にはそれを強く感じて大好きなナンバーです。この曲も早く音源化して欲しいなぁと思っています。
「ここでカヴァーをやろうか」と歌い始めたのはなんとジュリーの「時の過ぎゆくままに」でびっくりしたのですが、これがなんとももーちゃんの声にぴったりとハマっていて聴き惚れてしまいました。さらにカヴァーは続きこれまたびっくりの「男はつらいよ」です。そう、寅さんの主題歌です。これまたすっかりもーちゃんのオリジナル曲であるかのように自分のものにしていました。歌の途中に「わたくし、生まれも育ちも沖縄県石垣市登野城7丁目・・・」という寅さんの口上から始まるトークが挟まり、そこではずっと謎でありながら聞くに聞けなかったなぜ「もーちゃん」というニックネームなのかという疑問に対する答えが解明されました。
第一部の最後にここ何回かのライヴに鍵盤でサポートしている後輩の高嶺史さんが呼び込まれピアニカで参加して歌われたのは、もーちゃんのデビュー曲「見上げれば」です。この曲が震災後にラジオで流されていたことをきっかけに宮城県石巻と繋がったもーちゃんが、今年3月11日にその石巻でライヴを行いその会場に響いて震えたこの曲が、今宵は東京の会場で響き、さらにそこにはその石巻のライヴでお会いした主催された方も駆けつけて来ていらしており、僕の視界には彼女ともーちゃんが一緒に収まっていて得も言われぬ感慨に包まれました。
休憩明けは恒例のじゃんけん大会で石垣からのおみやげ争奪戦で盛り上がり、そこから始まった第二部はいよいよ島の先輩パーカッショニスト波照間剛さんを迎えてのセットです。いきなり「永久の夢」でもう休憩がなかったかのように一気にヴォルテージがマックスに昇りつめました。めちゃめちゃかっこいい曲なのですが、やはりパーカッションが入るとより一層高揚感が増します。続く「10年」もゆったり流れるような曲ながら波照間さんの叩き出す音が曲全体をクッキリと鮮やかにしている感じで、そうそうこれだよね!という心持ちでその音に身を任せました。
ここで昨夜の「白百合の宴」でも共演された石井幸枝さんがステージに呼ばれフルートを手に登場し、トリオ編成による「呼吸」をブルージィに演奏です。ジャズクラブで強めのお酒を手に聴いているような雰囲気で素敵です。
幸枝さんに替わっては、いい感じに出来上がりつつある高嶺さんが再び呼ばれ、ピアニカで参加しての「都バス」、そして「あいのうた」に収録されている「中央線」と明るく楽しいナンバーが続きます。先輩と後輩とのトリオ編成にもーちゃんも楽しそうです。
このまま盛り上がって終盤を終えるのかと思いきや、意表を突いて突然のカヴァー曲、それも「天城越え」です。もう完全にもーちゃんのレパートリーとなっているだけにコブシの入り方もぞくぞくするほどです。このような情歌も自分のものにしてしまう歌唱力はすごいと敬服しちゃいますし、何の曲だかわかったところでお客さんからは笑いが漏れるのですが、進んで行くうちに決してお遊びで歌ってみましたという感じではなく、引き込んでいってしまうのはさすがもーちゃんです。
ラストは、そうだこの曲がまだでしたという名曲「こだま」。歌詞のひとつひとつがきっちりと届いて響いてくるこの曲に今宵も涙腺崩壊寸前でしたし、実際に目頭を拭っている何人かのお客さんもステージ横の僕の席からは視界の端に見えていてもらい泣きしそうになりました。これだけ心を揺さぶる曲をこうして、今回は2夜連続で聴く事ができたのは、まるで僕の奥深くにある土壌に水を撒いてもらったかのようでした。
アンコールは再び高嶺さんが呼ばれ更に気持ちよくなった状態で登場。もーちゃんが梅雨入りしたはずの沖縄が灼熱の暑さという話をしている時に謎のメロディーをピアニカで奏でていて何かと思ったら「梅雨入りを音で表わしてみました」ということで場内爆笑です。このトリオでノリノリなナンバー「海へ行こう」が始まり、お客さんもコーラスで参加しての一体感です。
そしてもう1曲はアルバムのタイトルトラックである文字通りのラヴソング「愛のうた」です。ただこの曲もいわゆる君が好きだI LOVE YOUというだけの想いではなく、歌われている「君」は性別も年齢も関係なくそれぞれに対する形の「愛」を伝え届けてくれているように感じるのは、やはりもーちゃんの声と感性の持つ包容力なのでしょう。それがこんなおじさんの僕にさえ伝わってくる、届いてくるのですから、そのチカラは半端ないことは間違いありません。
こうして幕を閉じた今回の音夜祭も、時季はずれますが石垣からさわやかなうりずんの風を吹かせてくれたかのような時間でした。以前のライヴタイトルで自分の名前を織り込んで「喜幸哀楽」と名付けられていたものがありましたが、今夜のライヴのあとにその言葉を思い出しました。2時間ちょっとのライヴの中には確かに「喜び」「幸せ」「哀しみ」「楽しさ」のすべてが含まれていて、どの気持ちも素直に出していいんだよと歌を通して語りかけてくれているかのようです。本当にもーちゃん、石垣よしゆきさんの歌声はその文字の通り「喜び」と「幸せ」をもたらしてくれるのです。
Posted by Ken2 at
23:59
│Comments(0)
2018.6.1 白百合の宴@碑文谷・APIA40
2018年06月01日 / その他(沖縄)/ 石垣喜幸/ 迎里計
2018.6.1 白百合の宴~初夏の潮騒まつり~@碑文谷・APIA40

7年前に沖縄の音楽に出会いたくさんの自分にとって新しいミュージシャンの音と出会う中で、最初は民謡系とロック・ポップス系とのカテゴリーが存在して分けて考えていました。しばらくしてその分類にほとんど意味がない事に気付き始めたのです。ライヴを見に行っても双方のカテゴリーに収めていたミュージシャンが共演されていたり、レコーディングに参加されていたりと、そもそもカテゴリーに分けること自体に意味を感じなくなってきました。またそのライヴでの共演で新たなミュージシャンと出会うことが出来てその音楽にハマっていくうちに、あれ?この人とあの人も繋がっていたんだという70年代アメリカのウエストコーストミュージックシーンの相関図のような広がりが展開していったのです。今宵のライヴはまさしくそんな繋がり、沖縄の言葉で言うところの「結(ゆい)」を強く感じるものとなりました。

「白百合の宴」と銘打った今夜のイヴェントに行こうと最初決めたのはもーちゃんこと石垣よしゆきさんが久しぶりに東京に来てくれるし、ライヴハウスで聴かれるというポイントでした。予約してから詳細を見たら迎里計さんも出られる!ソロでも見に行くおふたりが一堂に会するなんてラッキーと思い、さらに、というよりこのイヴェントの核である池原コーイチさんも以前那覇での一合瓶ライヴで聴いたことがあるだけだったので、ちゃんと聴くとても良い機会となったのです。

学芸大学の住宅街の中にある会場に入ると、お店でのそれとはまた違ったライヴハウスならではの高揚感で期待は高まる一方です。トップバッターは池原コーイチさん。プロフィールを拝見すると多くのファンを持つ泡盛「白百合」「赤馬」を作られている池原酒造所の方でありながら、石垣島のフォークミュージック界の重鎮です。それくらいしか予備知識がないのですが、アコギで歌い始まるとなんとも骨太でありながら心の内側を繊細に描く曲でぐいぐいと引き込まれていきました。

今回のセットは一緒にツアーをされている石井幸枝さんとの共演です。幸枝さんは先週見に行った竹富島地唄いライヴにも参加されたフルート、オカリナ奏者で、コーイチさんの世界観に彩りと広がりを加えてくれています。その感じがなんとも心地よいのです。

途中からパーカッションのゆっきーこと国場幸孝さんも加わりさらに音の厚みが増します。こういう音響のしっかりした場でいくつもの楽器が交わるのを耳にするのが久しぶりだったので、バンドずきの自分にはもうそれだけで幸せです。

残念ながらコーイチさんの作品について語る知識はないのですが、安定感のあるセットでした。また随所にコーイチさんの後輩ミュージシャンを思い遣る心遣いや、逆に慕われる存在であることが感じられました。

短い休憩を挟んで二番手は迎里計さんの登場です。そのステージではいつも自分を笑顔にしてくれると同時に、心に訴えかけるように沁み込んでくる曲を聴かせてくれ、慌ただしい日々を過ごしている時をすこしゆっくりとそのペースをリセットしてくれます。今夜は石垣の先輩たちに囲まれてトークもいつになく島モードが入っていたようです。

島にいた頃はいつも観光客のお姉さんたちに恋していましたと歌われた「うりずんの人」でオープニング。もうすぐ音楽配信されるという寄り添うような優しい応援歌「がんばれの向こう側」、白百合を飲んで大人の階段昇った話からチューハイへと話が続きおなじみの「名も知らぬ友と夕暮れのガード下」へと続きます。計さんの書く歌詞は巧い表現ではないかも知れませんが等身大の日常を描いているので、歌われている光景や風景がたとえその場所にいったことがなくても脳裏にミュージックビデオのように流れてくるのです。

そして初めて計さんのライヴを見に行った時に、それまで朗らかな曲を歌う人という印象だった自分の心をがっちりと掴んだ深い曲「あざみの根っこ」を歌ってくれました。病魔に襲われた弟のために、棘で手を血だらけにしながらも自然の薬と言われるアザミの根っこ引き抜いて集めて行く兄を歌った切なくも奥深い歌で、毎回涙腺崩壊しそうになります。

先ほど書いた風景が浮かぶ曲の代表ともいえるのが竹富島を歌った「島の歩幅」です。このゆったりとした三拍子の曲は島の時や風の流れをリアルに感じさせてくれて心が安らぎます。今夜は幸枝さんがフルートで参加してくれて、さらに風を感じられる曲になって座っていた座席がどんどん柔らかく心地よいソファになっていくような感覚でした。

計さんのセットのラストは全員参加型コール&レスポンスの「ボッタリナオシ」です。数多くのイヴェントライヴ、対バンの経験を持つだけにその日初めて計さんを知ったお客さんをも自分の世界に引き込んでいくのはすごいなぁと毎回思います。今夜もみんな一緒に♪ボッタリ!のレスポンスで楽しい締めくくりとなりました。

そしてトリはいよいよもーちゃんこと石垣よしゆきさんの登場です。なにか大きくあたたかいもので自分を包み込んでくれるもーちゃんの歌声は、僕の耳をハートにして「俺はこの人に恋してるんじゃないか」と思っちゃうほどメロメロにしてくれるシンガーです。オープニング曲「10年」のハミングの歌い出しでもうとろけ始めました。

今回のステージは島の先輩ドラマー波照間剛さんがサポートに入り、それによりここ最近のもーちゃんのステージとは一味違ったものになっています。包み込むような優しさにギュっと力強さが加わったようなサウンドです。

その波照間さんの打ち出すビートでいつもより更にブルース色が濃くなった「呼吸」では持ってくるのを忘れてしまったので口(くち)カズーで間奏のソロが入りました。

3曲目は東京に居た頃に住んでいた街の大好きだった電車を歌った「中央線」。今年発表したアルバムにも収録されている軽妙なナンバーで、楽しいトークも交えてどんどん場を盛り上げていきます。

ここでせっかくだからともーちゃんが計さんをステージに招くといううれしいサプライズが。ふたりが同じライヴに出るだけでもウハウハなのにまさかの共演です。計さんの一五一会が加わって歌われたのはこれまた涙腺崩壊寸前曲「こだま」です。いつもこの曲を聴くとトロントロンになってしまうのですが、今夜は波照間さんのドラムスと計さんの奏でる音が加わり、両手で掬われて高みに持ち上げていかれるような感じになりました。

もーちゃんのセットのラストは、今回サポートでドラムスが加わると聞いて以来にわかに期待していた最近はなかなかライヴでは聴かれなくなった曲「永久の夢」です。もうイントロからキターーーーッ!という感じで、自分にとってキラーチューンであるこの曲はかっこいいとしか言いようがないほどかっこよく骨抜き状態で一緒に歌っちゃいました。曲が進につれて、終わらないで!終わらないで!って理不尽な思いに駆られたくらいです。

こうして3組のステージが終わりアンコールは出演者全員がステージに登場して「生活の柄」で応えてくれました。この曲の時にはみんなを仕切りながらも、それぞれを引き立てるように気配りを欠かさないコーイチさんの懐の深さを感じ、それによって出演者の後輩たちが気持ちよく楽しそうにセッションしている姿が印象的でした。

きっかけはもーちゃん出演だったから行ったライヴでしたが、トータルとしてとても楽しい一夜になりました。常々音楽の神様が住んでいらっしゃる場所だと思っている石垣島ですが、その思いはより一層確信へと変わりました。それは島では伝統芸能が盛んだとかいう事ではなく、生活の中に音楽が溢れているような場所である、そんな感覚です。それは冒頭に書いた「結」と共に音楽がもたらしてくれた幸福感として今夜のライヴの記憶に綴じ込みたいと思います。
7年前に沖縄の音楽に出会いたくさんの自分にとって新しいミュージシャンの音と出会う中で、最初は民謡系とロック・ポップス系とのカテゴリーが存在して分けて考えていました。しばらくしてその分類にほとんど意味がない事に気付き始めたのです。ライヴを見に行っても双方のカテゴリーに収めていたミュージシャンが共演されていたり、レコーディングに参加されていたりと、そもそもカテゴリーに分けること自体に意味を感じなくなってきました。またそのライヴでの共演で新たなミュージシャンと出会うことが出来てその音楽にハマっていくうちに、あれ?この人とあの人も繋がっていたんだという70年代アメリカのウエストコーストミュージックシーンの相関図のような広がりが展開していったのです。今宵のライヴはまさしくそんな繋がり、沖縄の言葉で言うところの「結(ゆい)」を強く感じるものとなりました。
「白百合の宴」と銘打った今夜のイヴェントに行こうと最初決めたのはもーちゃんこと石垣よしゆきさんが久しぶりに東京に来てくれるし、ライヴハウスで聴かれるというポイントでした。予約してから詳細を見たら迎里計さんも出られる!ソロでも見に行くおふたりが一堂に会するなんてラッキーと思い、さらに、というよりこのイヴェントの核である池原コーイチさんも以前那覇での一合瓶ライヴで聴いたことがあるだけだったので、ちゃんと聴くとても良い機会となったのです。
学芸大学の住宅街の中にある会場に入ると、お店でのそれとはまた違ったライヴハウスならではの高揚感で期待は高まる一方です。トップバッターは池原コーイチさん。プロフィールを拝見すると多くのファンを持つ泡盛「白百合」「赤馬」を作られている池原酒造所の方でありながら、石垣島のフォークミュージック界の重鎮です。それくらいしか予備知識がないのですが、アコギで歌い始まるとなんとも骨太でありながら心の内側を繊細に描く曲でぐいぐいと引き込まれていきました。
今回のセットは一緒にツアーをされている石井幸枝さんとの共演です。幸枝さんは先週見に行った竹富島地唄いライヴにも参加されたフルート、オカリナ奏者で、コーイチさんの世界観に彩りと広がりを加えてくれています。その感じがなんとも心地よいのです。
途中からパーカッションのゆっきーこと国場幸孝さんも加わりさらに音の厚みが増します。こういう音響のしっかりした場でいくつもの楽器が交わるのを耳にするのが久しぶりだったので、バンドずきの自分にはもうそれだけで幸せです。
残念ながらコーイチさんの作品について語る知識はないのですが、安定感のあるセットでした。また随所にコーイチさんの後輩ミュージシャンを思い遣る心遣いや、逆に慕われる存在であることが感じられました。
短い休憩を挟んで二番手は迎里計さんの登場です。そのステージではいつも自分を笑顔にしてくれると同時に、心に訴えかけるように沁み込んでくる曲を聴かせてくれ、慌ただしい日々を過ごしている時をすこしゆっくりとそのペースをリセットしてくれます。今夜は石垣の先輩たちに囲まれてトークもいつになく島モードが入っていたようです。
島にいた頃はいつも観光客のお姉さんたちに恋していましたと歌われた「うりずんの人」でオープニング。もうすぐ音楽配信されるという寄り添うような優しい応援歌「がんばれの向こう側」、白百合を飲んで大人の階段昇った話からチューハイへと話が続きおなじみの「名も知らぬ友と夕暮れのガード下」へと続きます。計さんの書く歌詞は巧い表現ではないかも知れませんが等身大の日常を描いているので、歌われている光景や風景がたとえその場所にいったことがなくても脳裏にミュージックビデオのように流れてくるのです。
そして初めて計さんのライヴを見に行った時に、それまで朗らかな曲を歌う人という印象だった自分の心をがっちりと掴んだ深い曲「あざみの根っこ」を歌ってくれました。病魔に襲われた弟のために、棘で手を血だらけにしながらも自然の薬と言われるアザミの根っこ引き抜いて集めて行く兄を歌った切なくも奥深い歌で、毎回涙腺崩壊しそうになります。
先ほど書いた風景が浮かぶ曲の代表ともいえるのが竹富島を歌った「島の歩幅」です。このゆったりとした三拍子の曲は島の時や風の流れをリアルに感じさせてくれて心が安らぎます。今夜は幸枝さんがフルートで参加してくれて、さらに風を感じられる曲になって座っていた座席がどんどん柔らかく心地よいソファになっていくような感覚でした。
計さんのセットのラストは全員参加型コール&レスポンスの「ボッタリナオシ」です。数多くのイヴェントライヴ、対バンの経験を持つだけにその日初めて計さんを知ったお客さんをも自分の世界に引き込んでいくのはすごいなぁと毎回思います。今夜もみんな一緒に♪ボッタリ!のレスポンスで楽しい締めくくりとなりました。
そしてトリはいよいよもーちゃんこと石垣よしゆきさんの登場です。なにか大きくあたたかいもので自分を包み込んでくれるもーちゃんの歌声は、僕の耳をハートにして「俺はこの人に恋してるんじゃないか」と思っちゃうほどメロメロにしてくれるシンガーです。オープニング曲「10年」のハミングの歌い出しでもうとろけ始めました。
今回のステージは島の先輩ドラマー波照間剛さんがサポートに入り、それによりここ最近のもーちゃんのステージとは一味違ったものになっています。包み込むような優しさにギュっと力強さが加わったようなサウンドです。
その波照間さんの打ち出すビートでいつもより更にブルース色が濃くなった「呼吸」では持ってくるのを忘れてしまったので口(くち)カズーで間奏のソロが入りました。
3曲目は東京に居た頃に住んでいた街の大好きだった電車を歌った「中央線」。今年発表したアルバムにも収録されている軽妙なナンバーで、楽しいトークも交えてどんどん場を盛り上げていきます。
ここでせっかくだからともーちゃんが計さんをステージに招くといううれしいサプライズが。ふたりが同じライヴに出るだけでもウハウハなのにまさかの共演です。計さんの一五一会が加わって歌われたのはこれまた涙腺崩壊寸前曲「こだま」です。いつもこの曲を聴くとトロントロンになってしまうのですが、今夜は波照間さんのドラムスと計さんの奏でる音が加わり、両手で掬われて高みに持ち上げていかれるような感じになりました。
もーちゃんのセットのラストは、今回サポートでドラムスが加わると聞いて以来にわかに期待していた最近はなかなかライヴでは聴かれなくなった曲「永久の夢」です。もうイントロからキターーーーッ!という感じで、自分にとってキラーチューンであるこの曲はかっこいいとしか言いようがないほどかっこよく骨抜き状態で一緒に歌っちゃいました。曲が進につれて、終わらないで!終わらないで!って理不尽な思いに駆られたくらいです。
こうして3組のステージが終わりアンコールは出演者全員がステージに登場して「生活の柄」で応えてくれました。この曲の時にはみんなを仕切りながらも、それぞれを引き立てるように気配りを欠かさないコーイチさんの懐の深さを感じ、それによって出演者の後輩たちが気持ちよく楽しそうにセッションしている姿が印象的でした。
きっかけはもーちゃん出演だったから行ったライヴでしたが、トータルとしてとても楽しい一夜になりました。常々音楽の神様が住んでいらっしゃる場所だと思っている石垣島ですが、その思いはより一層確信へと変わりました。それは島では伝統芸能が盛んだとかいう事ではなく、生活の中に音楽が溢れているような場所である、そんな感覚です。それは冒頭に書いた「結」と共に音楽がもたらしてくれた幸福感として今夜のライヴの記憶に綴じ込みたいと思います。
Posted by Ken2 at
23:59
│Comments(0)
2018.5.27 けい×けん(迎里計・野原健)@早稲田CanColor cafe
2018年05月27日 / その他(沖縄)/ 迎里計
2018.5.27 けい×けん(迎里計・野原健)@早稲田CanColor cafe

楽しかった前夜の「竹富島地唄いライブ」の余韻が残る中、今宵は昨夜のメンバーの中の野原健さん、迎里計さんによるユニット「ケイ×ケン」のライヴです。健さんは竹富島の方、計さんは石垣島白保のご出身ですが、おふたりは義理のご兄弟という間柄です。そこで今回ふたりでライヴをやってみようと言う事になったそうで、今宵が初のライヴとなりました。

オープニング・アクトとして昨夜も今夜も音響スタッフとして頑張っている川満太一朗さんが三線を手に登場。宮古島出身の青年で、自己紹介のあとまずは無伴奏で「なりやまあやぐ」を、そして唄三線で「酒田川」と続きます。宮古民謡はあまり聴く機会が多くないのでとても新鮮で、哀愁を帯びたような曲調にぐいぐいと引き込まれていきました。この2曲で終わってしまいましたが、もっとじっくりと聴いてみたかったなぁ。

短い準備のあといよいよ三線の健さん、一五一会の計さんによるステージです。一体どんな感じのライヴになるのかぁと思っていたらオープニングはおなじみの民謡で、計さんの出身地白保集落の"国歌"と言われている「白保節」からスタートです。八重山密度の高い客席だけにお囃子も自然発生的に入ります。健さんの力強い三線の音に計さんの奏でる繊細な一五一会の音色が絡んで、なんとも素敵な響きです。三線の音楽聴き始めたころには洋楽器とのアンサンブルは毛嫌いしていたのですが、今となっては何が嫌だったのだろうと思うほどです。その素敵な響きを引き継いだのはこれまた八重山を代表する教訓歌「デンサー節」だったのですが、ふたりの演奏なのにすごいなぁ笛の音色を感じます。聴けば聴くほどリアルでテープ流しているのかと思ったら、客席にいらっしゃる関係者の方が笛を吹かれていたのでした。まるで出会うべくして出会ったようなこの3つの音色に唄が乗り、心底染みる「デンサー節」となりました。

おふたりが自己紹介と、こうして一緒のステージに立つまでの流れなどをお話しされた後は計さんのオリジナルで、成人式の旅立ちの時を明るいメロディーに乗せて歌った「二十路の鳥」です。この曲も含めた計さんの作品や、以前参加した「白保フェスティバル」で感じた事なのですが、石垣島の方々の体内DNAには何故か「さよなら港」や「憧れのハワイ航路」の頃の昭和歌謡ずきが色濃く刷り込まれている気がしてなりません。

続いては健さんチョイスで昨夜も歌われた喜納昌吉さんの「東崎」です。健さんの声にもすごくマッチしていて、それ以前にきっとこ曲が大好きなのだろうなぁと感じるほど丁寧に歌われていました。

「今日は義理の兄との共演で妙な緊張がありまして」と語っていた計さん。それをどっしりと受け止め進めていく健さん。なんとも微笑ましくも素敵なご兄弟です。計さんのオリジナルで結婚式などのお祝いを歌った「スヨウニ節」に続き、これまた美しい八重山民謡「あがろーざ」だったのですが、計さんが「兄貴にこの曲はソロでと提案したらあっさり却下されたのですが、作戦を練って僕が音を減らして三線をフューチャーさせてみました。」と語っていた通り三線の音色が響いたのですが、優しい一五一会の音が子守唄らしいたおやかさを感じさせてくれたのもポイントでした。

それまで何度かイヴェントライヴで聴く機会があって計さんの名前はわからないけれど"干支の歌の人"というイメージが刷り込まれた曲「生まれ年音頭」へと進むうちに、先ほどのDNAの話じゃないですが石垣島ではお祝い事はものすごく大切に祝われているのだなぁ、人と人との結びつきが強いのだろうなぁと感じさせてくれる計さんの曲たちです。ソロのライヴでは何度かお聴きしているのですが、こうして健さんの三線が入るとピタッとハマります。一部のラストは山之口貘さんの詩に高田渡さんがメロディーをつけた曲で、自分が小学生だった頃に近所の大学生のお兄さんの部屋に宿題教わりに行ったりするとよく流れていた「生活の柄」が歌われてびっくりです。この選曲に自分の記憶の奥の方に腕まくりした手を突っ込んで引っ張り出してくるような感じでした。以前、計さんがライヴで高田さんの「値上げ」カヴァーされていたので、これも計さん選曲かな。

休憩を挟んでの第二部はじめはそれぞれソロで何かをやるコーナーらしいのですが、まず登場した健さんはちょっと反則(?)して「今日は会場に素敵なミュージシャンの方がたくさん来ているのですよ。その中の1人と一緒に演りたいと思います。」と紹介されて呼ばれたのは八重山民謡の歌手の方で大迫吟子さんとおっしゃるそうです。健さんの三線で始まったのはドラマ「ちゅらさん」でイントロだけは有名になった「小浜節 」です。八重山民謡の女性歌手の方の特徴である高く伸びる声が響き、健さんとの掛け合いも良い感じです。それと客席に八重山の方がたくさんいらして、感心したのですが1コーラス終わると絶妙なタイミングで「いよっ!」みたいな掛け声と共に拍手が送られ、それが妙にカッコ良かったです。

次は計さんのコーナーで選んでくれた曲はオリジナルで、昨年初めて聴いて"一耳惚れ"した曲「あざみの根っこ」です。もう曲紹介でタイトル聞いただけで涙腺緩んできそうになったほどです。歌詞の一言一言をしっかりと噛み締めて聴いたこの曲には、選んでくれた計さんにもう"ミーファイユ"の言葉しか浮かびません。

続いてはTHE SAKISHIMA meetingのナンバーで「島風」、そして計さんのナンバー「ボッタリナオシ」だったのですが、この曲は途中でタイトルの歌詞のコール&レスポンスがお約束なのですが、客席にいたお子さんがそう聴こえたのか、間違えて覚えてしまったのか大きな声で"ポッチャリ!ポッチャリ!"歌い出し、途中から計さんもポッチャリに歌詞を変えちゃうという茶目っ気たっぷりな流れに。ボッタリナオシするよりも、きっとポッチャリ直す方がはるかに大変だと思いますけれどね。

「まり!歌うか!」と健さんに突然呼ばれたのは竹富島の歌姫、上勢頭まりさんです。歌ってくれたのはもちろん下地イサムさんのナンバーで「あの夏の日」です。昨夜歌う前にあれだけ緊張されていた宮古方言の曲で、今夜も「歌詞を間違えてしまったらごめんなさい」と歌われる前におっしゃられていましたが、大丈夫です。なんせこの曲の歌詞、唯一わかるのは"学校"という一言なのですから。昨夜も感銘を受けたのですが、今夜の会場は天井が高く音の響き方が気持ち良い場所なので、まりさんの伸びやかな高い声が三線と一五一会の音色と共に一層空間に染み渡るように広がり、青空の下サトウキビ畑の真ん中で風に吹かれながら聞いているかのようでした。

ここから2曲はBorn ti Caftaのナンバーの明るく楽しい「宴」と「音遊び」です。考えたらぼーんちカフタは計さんと実兄の中さんとの兄弟ユニットで、けい×けんは義兄弟ユニットです。よほどの弟キャラなのか、これだけ"兄"とユニットを組んでいるミュージシャンはそういないと思います。健さんとの息もぴったりでこの流れでグングンと昇っていきました。そしてラストはみんな大好きな「うたのうた」です。三線が入ったこの曲もいいなぁ。最後はもちろん♪ラーラーラー…の大合唱で美しく締めくくられました。

アンコールはTHE SAKISHIMA meetingの「松原ユンタ」です。健さん指導のもと"うやき よーゆばなうれ"のコール&レスポンスのトレーニングからのスタートです。「うたのうた」のコーラスで声出しているのでお囃子もバッチリです。健さんの三線もブルースギターのように響き渡りかっこよかったです。そしてもう一曲、この素敵な夜を締めくくるのは計さんのアルバムの中でも大好きな曲で、ライヴでも外せない「しずく」です。この曲も涙腺ヤバくなる曲で、最後は♪ラーラーラー…のコーラスの大合唱でとてもあたたかい気持ちにさせてくれる曲です。そして今夜は三線も入りその感じが増幅したように感じました。

けい×けんの初ステージは、さながらその音で別の場所に連れて行ってくれたかのような時間でした。それでもライヴが終わり外に出てみてもそこには白砂の道はなく、アスファルト舗装された片側三車線の道路が走っていて、慌ててまだ島の時の流れの余韻が残る店内に戻ったのです。ライヴ後半に「僕は本当はみなさんに楽しんでいただく立場なのですが、ごめんなさい、今日は僕が一番楽しいです!」と計さんが語っていましたが、それはきっと健さんも同じ事だろうと思いますし、あんなに楽しそうにステージを進めていくおふたりを見ているこちらは実はそれ以上に楽しませてもらっているのですよ。なかなか機会を作るのは難しいかもしれませんが、またこの義兄弟ユニットの音に浸るのを楽しみにしています。

楽しかった前夜の「竹富島地唄いライブ」の余韻が残る中、今宵は昨夜のメンバーの中の野原健さん、迎里計さんによるユニット「ケイ×ケン」のライヴです。健さんは竹富島の方、計さんは石垣島白保のご出身ですが、おふたりは義理のご兄弟という間柄です。そこで今回ふたりでライヴをやってみようと言う事になったそうで、今宵が初のライヴとなりました。

オープニング・アクトとして昨夜も今夜も音響スタッフとして頑張っている川満太一朗さんが三線を手に登場。宮古島出身の青年で、自己紹介のあとまずは無伴奏で「なりやまあやぐ」を、そして唄三線で「酒田川」と続きます。宮古民謡はあまり聴く機会が多くないのでとても新鮮で、哀愁を帯びたような曲調にぐいぐいと引き込まれていきました。この2曲で終わってしまいましたが、もっとじっくりと聴いてみたかったなぁ。

短い準備のあといよいよ三線の健さん、一五一会の計さんによるステージです。一体どんな感じのライヴになるのかぁと思っていたらオープニングはおなじみの民謡で、計さんの出身地白保集落の"国歌"と言われている「白保節」からスタートです。八重山密度の高い客席だけにお囃子も自然発生的に入ります。健さんの力強い三線の音に計さんの奏でる繊細な一五一会の音色が絡んで、なんとも素敵な響きです。三線の音楽聴き始めたころには洋楽器とのアンサンブルは毛嫌いしていたのですが、今となっては何が嫌だったのだろうと思うほどです。その素敵な響きを引き継いだのはこれまた八重山を代表する教訓歌「デンサー節」だったのですが、ふたりの演奏なのにすごいなぁ笛の音色を感じます。聴けば聴くほどリアルでテープ流しているのかと思ったら、客席にいらっしゃる関係者の方が笛を吹かれていたのでした。まるで出会うべくして出会ったようなこの3つの音色に唄が乗り、心底染みる「デンサー節」となりました。

おふたりが自己紹介と、こうして一緒のステージに立つまでの流れなどをお話しされた後は計さんのオリジナルで、成人式の旅立ちの時を明るいメロディーに乗せて歌った「二十路の鳥」です。この曲も含めた計さんの作品や、以前参加した「白保フェスティバル」で感じた事なのですが、石垣島の方々の体内DNAには何故か「さよなら港」や「憧れのハワイ航路」の頃の昭和歌謡ずきが色濃く刷り込まれている気がしてなりません。

続いては健さんチョイスで昨夜も歌われた喜納昌吉さんの「東崎」です。健さんの声にもすごくマッチしていて、それ以前にきっとこ曲が大好きなのだろうなぁと感じるほど丁寧に歌われていました。

「今日は義理の兄との共演で妙な緊張がありまして」と語っていた計さん。それをどっしりと受け止め進めていく健さん。なんとも微笑ましくも素敵なご兄弟です。計さんのオリジナルで結婚式などのお祝いを歌った「スヨウニ節」に続き、これまた美しい八重山民謡「あがろーざ」だったのですが、計さんが「兄貴にこの曲はソロでと提案したらあっさり却下されたのですが、作戦を練って僕が音を減らして三線をフューチャーさせてみました。」と語っていた通り三線の音色が響いたのですが、優しい一五一会の音が子守唄らしいたおやかさを感じさせてくれたのもポイントでした。

それまで何度かイヴェントライヴで聴く機会があって計さんの名前はわからないけれど"干支の歌の人"というイメージが刷り込まれた曲「生まれ年音頭」へと進むうちに、先ほどのDNAの話じゃないですが石垣島ではお祝い事はものすごく大切に祝われているのだなぁ、人と人との結びつきが強いのだろうなぁと感じさせてくれる計さんの曲たちです。ソロのライヴでは何度かお聴きしているのですが、こうして健さんの三線が入るとピタッとハマります。一部のラストは山之口貘さんの詩に高田渡さんがメロディーをつけた曲で、自分が小学生だった頃に近所の大学生のお兄さんの部屋に宿題教わりに行ったりするとよく流れていた「生活の柄」が歌われてびっくりです。この選曲に自分の記憶の奥の方に腕まくりした手を突っ込んで引っ張り出してくるような感じでした。以前、計さんがライヴで高田さんの「値上げ」カヴァーされていたので、これも計さん選曲かな。

休憩を挟んでの第二部はじめはそれぞれソロで何かをやるコーナーらしいのですが、まず登場した健さんはちょっと反則(?)して「今日は会場に素敵なミュージシャンの方がたくさん来ているのですよ。その中の1人と一緒に演りたいと思います。」と紹介されて呼ばれたのは八重山民謡の歌手の方で大迫吟子さんとおっしゃるそうです。健さんの三線で始まったのはドラマ「ちゅらさん」でイントロだけは有名になった「小浜節 」です。八重山民謡の女性歌手の方の特徴である高く伸びる声が響き、健さんとの掛け合いも良い感じです。それと客席に八重山の方がたくさんいらして、感心したのですが1コーラス終わると絶妙なタイミングで「いよっ!」みたいな掛け声と共に拍手が送られ、それが妙にカッコ良かったです。

次は計さんのコーナーで選んでくれた曲はオリジナルで、昨年初めて聴いて"一耳惚れ"した曲「あざみの根っこ」です。もう曲紹介でタイトル聞いただけで涙腺緩んできそうになったほどです。歌詞の一言一言をしっかりと噛み締めて聴いたこの曲には、選んでくれた計さんにもう"ミーファイユ"の言葉しか浮かびません。

続いてはTHE SAKISHIMA meetingのナンバーで「島風」、そして計さんのナンバー「ボッタリナオシ」だったのですが、この曲は途中でタイトルの歌詞のコール&レスポンスがお約束なのですが、客席にいたお子さんがそう聴こえたのか、間違えて覚えてしまったのか大きな声で"ポッチャリ!ポッチャリ!"歌い出し、途中から計さんもポッチャリに歌詞を変えちゃうという茶目っ気たっぷりな流れに。ボッタリナオシするよりも、きっとポッチャリ直す方がはるかに大変だと思いますけれどね。

「まり!歌うか!」と健さんに突然呼ばれたのは竹富島の歌姫、上勢頭まりさんです。歌ってくれたのはもちろん下地イサムさんのナンバーで「あの夏の日」です。昨夜歌う前にあれだけ緊張されていた宮古方言の曲で、今夜も「歌詞を間違えてしまったらごめんなさい」と歌われる前におっしゃられていましたが、大丈夫です。なんせこの曲の歌詞、唯一わかるのは"学校"という一言なのですから。昨夜も感銘を受けたのですが、今夜の会場は天井が高く音の響き方が気持ち良い場所なので、まりさんの伸びやかな高い声が三線と一五一会の音色と共に一層空間に染み渡るように広がり、青空の下サトウキビ畑の真ん中で風に吹かれながら聞いているかのようでした。

ここから2曲はBorn ti Caftaのナンバーの明るく楽しい「宴」と「音遊び」です。考えたらぼーんちカフタは計さんと実兄の中さんとの兄弟ユニットで、けい×けんは義兄弟ユニットです。よほどの弟キャラなのか、これだけ"兄"とユニットを組んでいるミュージシャンはそういないと思います。健さんとの息もぴったりでこの流れでグングンと昇っていきました。そしてラストはみんな大好きな「うたのうた」です。三線が入ったこの曲もいいなぁ。最後はもちろん♪ラーラーラー…の大合唱で美しく締めくくられました。

アンコールはTHE SAKISHIMA meetingの「松原ユンタ」です。健さん指導のもと"うやき よーゆばなうれ"のコール&レスポンスのトレーニングからのスタートです。「うたのうた」のコーラスで声出しているのでお囃子もバッチリです。健さんの三線もブルースギターのように響き渡りかっこよかったです。そしてもう一曲、この素敵な夜を締めくくるのは計さんのアルバムの中でも大好きな曲で、ライヴでも外せない「しずく」です。この曲も涙腺ヤバくなる曲で、最後は♪ラーラーラー…のコーラスの大合唱でとてもあたたかい気持ちにさせてくれる曲です。そして今夜は三線も入りその感じが増幅したように感じました。

けい×けんの初ステージは、さながらその音で別の場所に連れて行ってくれたかのような時間でした。それでもライヴが終わり外に出てみてもそこには白砂の道はなく、アスファルト舗装された片側三車線の道路が走っていて、慌ててまだ島の時の流れの余韻が残る店内に戻ったのです。ライヴ後半に「僕は本当はみなさんに楽しんでいただく立場なのですが、ごめんなさい、今日は僕が一番楽しいです!」と計さんが語っていましたが、それはきっと健さんも同じ事だろうと思いますし、あんなに楽しそうにステージを進めていくおふたりを見ているこちらは実はそれ以上に楽しませてもらっているのですよ。なかなか機会を作るのは難しいかもしれませんが、またこの義兄弟ユニットの音に浸るのを楽しみにしています。
Posted by Ken2 at
23:59
│Comments(0)
2018.5.26 竹富島地唄いライブ@小岩・こだま
2018年05月26日 / その他(沖縄)/ 萬木忍/ 迎里計
2018.5.26 竹富島地唄いライブ@小岩・沖縄料理 居酒や こだま

今年も年に一度のお楽しみ、竹富島の地唄の方々が東京にやって来てくれる「地唄いライブ」が開催されました。信仰の息づく島にはたくさんの神事祭事があり、それを彩り司り奉納される音楽があり、その行事以外で、ましてや島以外どころか遠く離れた東京で聴くことができる機会はそうそうあるものではありません。と言ってもの決して堅苦しい宗教音楽といった類ではなく、島に綿々と受け継がれいる生活に根差した音楽が楽しめるのです。加えて祭りには欠かせない要素でもあるみんなで楽しむ要素も十分に織り込まれた、いわば数時間の竹富島体験なのです。会場も竹富ご出身の方たちや島が大好きなファンで満席です。

人口350人ほどの島の5人がステージに立つのですからどれだけ音楽が根付いている島なのかという事がわかります。新田長男さん、内盛正聖さん、野原健さん、萬木忍さん、そして上勢頭まりさん、この方たちは所謂私たちが考える「プロのミュージシャン」とはちょっと違い、普段は普通の生活をされていて神事祭事の際に奉納される舞踊などで唄三線を務める「地唄い」の方たちなのです。周囲9kmほどの竹富島にはアイノタ(東集落)、インノタ(西集落)、ナージ(仲筋集落)という3つの集落があります。と言ってもちょっと歩くと隣の集落に入る感じですし、実際歩いてみてもその境は良くわからず、観光客の自分にはひとつのこじんまりとした集落と思えるほどです。それでも集落ごとに神事祭事があったり、今日ステージにいる5人のみなさんもそれぞれの集落で地唄いを務めていらっしゃるので、いっしょに演奏することは滅多にないというので驚きです。

ライブで演奏された曲を詳しく順を追ってお話できれば良いのですが、島の神事祭事で演奏される曲についてはまったく知識もないのでそれ以外の知っている曲についてしか語ることはできませんし、あまり楽しくてメモを取る事さえ忘れていたので順不同になります。ただ島で古くから歌い継がれてきた祭事の曲は、素朴でありながらもそこにたくさんの想いや願い、祈りが込められている感じがして、緊張と別の背筋が伸びるような神聖である感覚と同時に、生活を垣間見ることができているようなそんな気持ちにさせてくれたことは確かです。

メンバーの中で最長老である新田長男さんは「今年も生きて東京に来ることができました」というご挨拶で場内の笑いを取り、唄三線に太鼓にと大活躍です。新田さんは拝顔するだけで御利益がありそうな、まるで八重山の神事に降臨されるみるく(弥勒)様のお面のような風貌で拝みたくなってしまうほどです。

お馴染みの民謡やポップスもたくさん織り込まれました。今年もこうしてみなさんに逢えた嬉しさをと披露された「めでたい節」では、島の宴会部長として君臨する内盛正聖さんが、さっそくお客さんを引き込んで面白おかしい踊りで場内を沸かせます。

野原健さんは、同級生である大島保克さんのナンバー「赤ゆら」を歌ってくれたり、お客さんも一緒に口ずさめる僕も大好きな曲「うりずんの詩」を聴かせてくれました。また笛の名手ですので厳粛な空気を醸し出す美しい笛の音を響かせてくれました。

自分は7年前までは小さな瓶に入った星の砂の故郷としてしか認識がなく、名前は知っていてもどこにあるかさえも知らなかった竹富島ですが、沖縄本島を旅して三線の音に興味を持ち、動画サイトで検索して偶然その演奏を耳にし、その音に呼ばれているような気がして数か月後には島の西桟橋に立っていたという出会いを持つ萬木忍さん。この偶然がなければ自分は今夜この場にはいなかったはずですし、今夜も忍さんの唄三線に自分を竹富島に向かわせた吸引力を改めて感じました。

竹富の歌姫、上勢頭まりさん。彼女の伸びる澄んだ声はそれだけで八重山民謡の持つ神々しい世界へと導いてくれます。昨年のライブでは新良幸人さん・サトウユウコさんの名曲「浄夜」を歌い上げてくださり鳥肌が立ったのですが、今回はやはりこのおふたりのアルバムにも収められている下地イサムさんの作品「あの夏の日」を歌われました。八重山方言とはまったく異なった、異なるどころかほぼ異国の言葉に近い感のある宮古方言で歌われている曲なのですが、しっかりと酔わせてくれました。

今夜はゲストがお二方いらっしゃいました。石垣島白保出身で自分も大好きなアーティストの迎里計さんは途中から一五一会でサポートに入りました。野原健さんとは義理のご兄弟で、白保に帰省するよりも多く竹富に行かれていると語っていらっしゃいました。

計さんはオリジナル曲「名も知らぬ友と夕暮れのガード下」を歌い、楽しいこの曲には宴会部長の内盛さんが盛り上げカズーで参加して、いつもにも増して楽しいヴァージョンになり、お客さんもみんな笑顔になっていました。

もうお一方はフルート、オカリナ奏者で、忍さんのレコーディングに参加されたりと交流のある石井幸枝さんです。忍さんのソロコーナーで歌われた名曲「とぅばらーま」では笛や合いの手のパートをフルートの音色で再現されたのですが、その優しい音色はまるで背景に満月を浮かび上がらせてステージに海の水面に輝く光の道を描いているかのようでした。

短い休憩を挟んでたっぷり聴かせてくれたセットですが、二部の始めでは飛び入りで幼稚園児くらいの男の子が武将の装束で扇を持って「渡りぞう・瀧落菅撹」の演奏に合わせて舞うというサプライズが。島のお子さんなのでしょうか、こうして受け継がれていることに「伝承」という二文字が浮かびました。そして「赤田首里殿内」では再び宴会部長が主役です。客席を周りターゲットを見つけては立たせて一緒に意味不明な踊りを踊り場内大盛り上がりです。選ばれたお客さんたちも恥ずかしがって固辞するわけでもなく、一緒にこの場を盛り上げます。居酒屋さんのライヴでありがちな演奏関係なしに飲み会の態で盛り上がり大騒ぎしているのとは違い、このような盛り上がりは大歓迎ですし、会場を埋めている全員の竹富島への深い愛情を感じました。

小さな島ながらここを発祥とする言わばご当地ソングの民謡も多数あり「仲筋ぬヌベーマ」「安里屋節」などを聴かせてくれましたが、当たり前の話なのですが竹富の方々が唄っているだけでものすごく「本物だぁ!」という感じがします。もちろんどこのどなたが唄ってもニセモノはないのですが、気分の問題なのでしょうね。そんな思いもあって今年のセットはいつもにも増して竹富島カラーが全面に押し出されていたように感じたのですが、あとから振り返ってみるとお馴染みのBEGINの曲が1曲もなかったのです。自分も好きなバンドですし、みんなが知っている曲もたくさんあり盛り上がるし、例えば「竹富島であいましょう」はある意味ご当地ソングのはずなのですが、BEGINナンバーが無かったことにより巧い表現ではないかもしれませんが「観光客向けライヴ感」が薄まったのかもしれません。それによってもっと竹富島の自然の姿を感じる結果となったのではないでしょうか。

休憩を挟んでたっぷり三時間近く楽しませてくれたライヴのラストは全員参加型の定番「安里屋ゆんた」の合いの手大合唱です。そして終わりかなぁと思ったら野原さんの「もう1曲やろう」という嬉しい言葉とともに思わぬ曲がゲストお2人も加えた出演者全員で披露されたのです。この曲「島の歩幅」は計さんの作品で竹富島に想いを馳せて作られた自分の大好きな曲なのです。タイトルの通り、島で流れる時間に身を委ねるとせかせかと歩くのではなくなるという、ものすごくわかる感覚をゆったりとしたメロディーに乗せて歌った曲なのです。この感覚は島の外の人が抱くものなのでしょうが、それを島の方々が歌われているとなんとも感慨深いものがあり、先ほどのBEGINの話とは手のひらを返したように矛盾してしまいますが、いつも計さんのソロで聴いているこの曲が今夜竹富島のご当地ソングになったような気がしました。とても素敵な選曲でした。

こうして今年の地唄いライブは幕を閉じました。毎年東京で竹富島の風を、空気を、時の流れを感じさせてもらえるのは正に「世果報(ゆがふ)」な時間であります。ライヴ中に忍さんが仰った「島の祭事で歌われる曲をこうゆう場で歌っていいものだろうかと考える部分もあります」という言葉がとても心に響き、それでも大切にされているこれらの曲を祭事の場ではなくライヴステージで聴かせてもらえた事は本当に「世果報」だと再認識すると同時に、毎年の事ながらいつの日かこれらの曲が本来の姿として演奏される場で体験してみたいという思いに駆られるのです。冒頭にも書いた通り音楽を生業とされているミュージシャンの方たちのライヴではないのですが、こうして受け継がれてきた音楽をきっと子供のころから聴いて育ち、練習を繰り返し習得し生活の一部として演奏し唄われている事に、これこそが音楽の原点なんだろうなと感じた夜でした。
今年も年に一度のお楽しみ、竹富島の地唄の方々が東京にやって来てくれる「地唄いライブ」が開催されました。信仰の息づく島にはたくさんの神事祭事があり、それを彩り司り奉納される音楽があり、その行事以外で、ましてや島以外どころか遠く離れた東京で聴くことができる機会はそうそうあるものではありません。と言ってもの決して堅苦しい宗教音楽といった類ではなく、島に綿々と受け継がれいる生活に根差した音楽が楽しめるのです。加えて祭りには欠かせない要素でもあるみんなで楽しむ要素も十分に織り込まれた、いわば数時間の竹富島体験なのです。会場も竹富ご出身の方たちや島が大好きなファンで満席です。
人口350人ほどの島の5人がステージに立つのですからどれだけ音楽が根付いている島なのかという事がわかります。新田長男さん、内盛正聖さん、野原健さん、萬木忍さん、そして上勢頭まりさん、この方たちは所謂私たちが考える「プロのミュージシャン」とはちょっと違い、普段は普通の生活をされていて神事祭事の際に奉納される舞踊などで唄三線を務める「地唄い」の方たちなのです。周囲9kmほどの竹富島にはアイノタ(東集落)、インノタ(西集落)、ナージ(仲筋集落)という3つの集落があります。と言ってもちょっと歩くと隣の集落に入る感じですし、実際歩いてみてもその境は良くわからず、観光客の自分にはひとつのこじんまりとした集落と思えるほどです。それでも集落ごとに神事祭事があったり、今日ステージにいる5人のみなさんもそれぞれの集落で地唄いを務めていらっしゃるので、いっしょに演奏することは滅多にないというので驚きです。
ライブで演奏された曲を詳しく順を追ってお話できれば良いのですが、島の神事祭事で演奏される曲についてはまったく知識もないのでそれ以外の知っている曲についてしか語ることはできませんし、あまり楽しくてメモを取る事さえ忘れていたので順不同になります。ただ島で古くから歌い継がれてきた祭事の曲は、素朴でありながらもそこにたくさんの想いや願い、祈りが込められている感じがして、緊張と別の背筋が伸びるような神聖である感覚と同時に、生活を垣間見ることができているようなそんな気持ちにさせてくれたことは確かです。
メンバーの中で最長老である新田長男さんは「今年も生きて東京に来ることができました」というご挨拶で場内の笑いを取り、唄三線に太鼓にと大活躍です。新田さんは拝顔するだけで御利益がありそうな、まるで八重山の神事に降臨されるみるく(弥勒)様のお面のような風貌で拝みたくなってしまうほどです。
お馴染みの民謡やポップスもたくさん織り込まれました。今年もこうしてみなさんに逢えた嬉しさをと披露された「めでたい節」では、島の宴会部長として君臨する内盛正聖さんが、さっそくお客さんを引き込んで面白おかしい踊りで場内を沸かせます。
野原健さんは、同級生である大島保克さんのナンバー「赤ゆら」を歌ってくれたり、お客さんも一緒に口ずさめる僕も大好きな曲「うりずんの詩」を聴かせてくれました。また笛の名手ですので厳粛な空気を醸し出す美しい笛の音を響かせてくれました。
自分は7年前までは小さな瓶に入った星の砂の故郷としてしか認識がなく、名前は知っていてもどこにあるかさえも知らなかった竹富島ですが、沖縄本島を旅して三線の音に興味を持ち、動画サイトで検索して偶然その演奏を耳にし、その音に呼ばれているような気がして数か月後には島の西桟橋に立っていたという出会いを持つ萬木忍さん。この偶然がなければ自分は今夜この場にはいなかったはずですし、今夜も忍さんの唄三線に自分を竹富島に向かわせた吸引力を改めて感じました。
竹富の歌姫、上勢頭まりさん。彼女の伸びる澄んだ声はそれだけで八重山民謡の持つ神々しい世界へと導いてくれます。昨年のライブでは新良幸人さん・サトウユウコさんの名曲「浄夜」を歌い上げてくださり鳥肌が立ったのですが、今回はやはりこのおふたりのアルバムにも収められている下地イサムさんの作品「あの夏の日」を歌われました。八重山方言とはまったく異なった、異なるどころかほぼ異国の言葉に近い感のある宮古方言で歌われている曲なのですが、しっかりと酔わせてくれました。
今夜はゲストがお二方いらっしゃいました。石垣島白保出身で自分も大好きなアーティストの迎里計さんは途中から一五一会でサポートに入りました。野原健さんとは義理のご兄弟で、白保に帰省するよりも多く竹富に行かれていると語っていらっしゃいました。
計さんはオリジナル曲「名も知らぬ友と夕暮れのガード下」を歌い、楽しいこの曲には宴会部長の内盛さんが盛り上げカズーで参加して、いつもにも増して楽しいヴァージョンになり、お客さんもみんな笑顔になっていました。
もうお一方はフルート、オカリナ奏者で、忍さんのレコーディングに参加されたりと交流のある石井幸枝さんです。忍さんのソロコーナーで歌われた名曲「とぅばらーま」では笛や合いの手のパートをフルートの音色で再現されたのですが、その優しい音色はまるで背景に満月を浮かび上がらせてステージに海の水面に輝く光の道を描いているかのようでした。
短い休憩を挟んでたっぷり聴かせてくれたセットですが、二部の始めでは飛び入りで幼稚園児くらいの男の子が武将の装束で扇を持って「渡りぞう・瀧落菅撹」の演奏に合わせて舞うというサプライズが。島のお子さんなのでしょうか、こうして受け継がれていることに「伝承」という二文字が浮かびました。そして「赤田首里殿内」では再び宴会部長が主役です。客席を周りターゲットを見つけては立たせて一緒に意味不明な踊りを踊り場内大盛り上がりです。選ばれたお客さんたちも恥ずかしがって固辞するわけでもなく、一緒にこの場を盛り上げます。居酒屋さんのライヴでありがちな演奏関係なしに飲み会の態で盛り上がり大騒ぎしているのとは違い、このような盛り上がりは大歓迎ですし、会場を埋めている全員の竹富島への深い愛情を感じました。
小さな島ながらここを発祥とする言わばご当地ソングの民謡も多数あり「仲筋ぬヌベーマ」「安里屋節」などを聴かせてくれましたが、当たり前の話なのですが竹富の方々が唄っているだけでものすごく「本物だぁ!」という感じがします。もちろんどこのどなたが唄ってもニセモノはないのですが、気分の問題なのでしょうね。そんな思いもあって今年のセットはいつもにも増して竹富島カラーが全面に押し出されていたように感じたのですが、あとから振り返ってみるとお馴染みのBEGINの曲が1曲もなかったのです。自分も好きなバンドですし、みんなが知っている曲もたくさんあり盛り上がるし、例えば「竹富島であいましょう」はある意味ご当地ソングのはずなのですが、BEGINナンバーが無かったことにより巧い表現ではないかもしれませんが「観光客向けライヴ感」が薄まったのかもしれません。それによってもっと竹富島の自然の姿を感じる結果となったのではないでしょうか。
休憩を挟んでたっぷり三時間近く楽しませてくれたライヴのラストは全員参加型の定番「安里屋ゆんた」の合いの手大合唱です。そして終わりかなぁと思ったら野原さんの「もう1曲やろう」という嬉しい言葉とともに思わぬ曲がゲストお2人も加えた出演者全員で披露されたのです。この曲「島の歩幅」は計さんの作品で竹富島に想いを馳せて作られた自分の大好きな曲なのです。タイトルの通り、島で流れる時間に身を委ねるとせかせかと歩くのではなくなるという、ものすごくわかる感覚をゆったりとしたメロディーに乗せて歌った曲なのです。この感覚は島の外の人が抱くものなのでしょうが、それを島の方々が歌われているとなんとも感慨深いものがあり、先ほどのBEGINの話とは手のひらを返したように矛盾してしまいますが、いつも計さんのソロで聴いているこの曲が今夜竹富島のご当地ソングになったような気がしました。とても素敵な選曲でした。
こうして今年の地唄いライブは幕を閉じました。毎年東京で竹富島の風を、空気を、時の流れを感じさせてもらえるのは正に「世果報(ゆがふ)」な時間であります。ライヴ中に忍さんが仰った「島の祭事で歌われる曲をこうゆう場で歌っていいものだろうかと考える部分もあります」という言葉がとても心に響き、それでも大切にされているこれらの曲を祭事の場ではなくライヴステージで聴かせてもらえた事は本当に「世果報」だと再認識すると同時に、毎年の事ながらいつの日かこれらの曲が本来の姿として演奏される場で体験してみたいという思いに駆られるのです。冒頭にも書いた通り音楽を生業とされているミュージシャンの方たちのライヴではないのですが、こうして受け継がれてきた音楽をきっと子供のころから聴いて育ち、練習を繰り返し習得し生活の一部として演奏し唄われている事に、これこそが音楽の原点なんだろうなと感じた夜でした。
Posted by Ken2 at
23:59
│Comments(0)